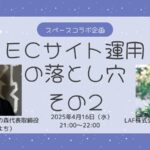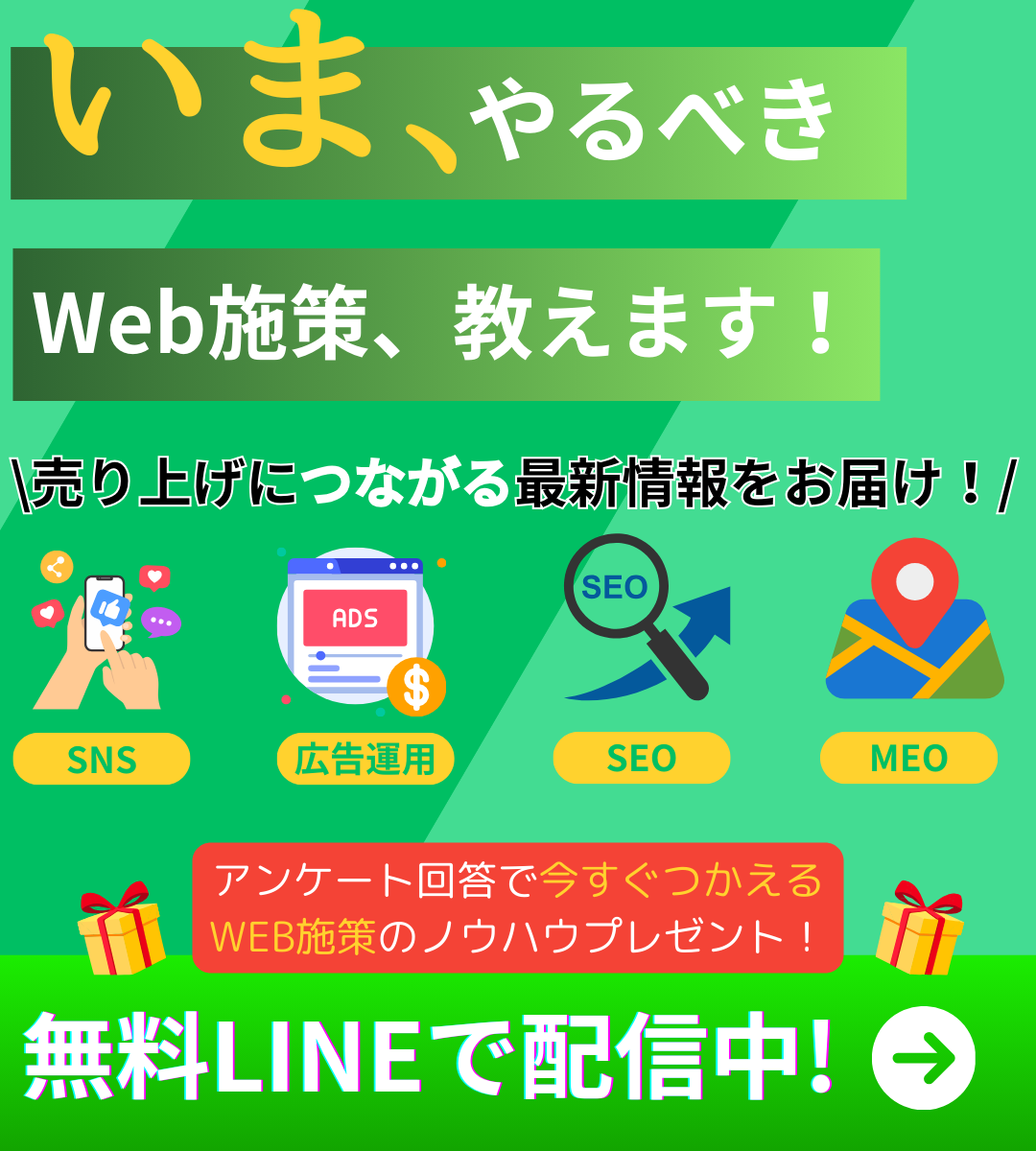「自社に合うデジタルマーケティング組織図をどう設計すればよいかわからない」
「マーケティング部門と営業部門の役割や連携方法が曖昧で、効果的な体制を組めていない」
といった悩みを抱えていませんか?
本記事では、そんな課題を解決するために、デジタルマーケティングの組織体制を整える7つのポイントを徹底解説します。
部門間の情報共有を円滑化する方法や、データドリブンな意思決定プロセスの確立など、実践的なノウハウを具体例とともに紹介。
さらに、よくある失敗パターンとその対処法にも触れ、組織づくりをスムーズに進める秘訣をお伝えします。理想のデジタルマーケティング体制を構築するなら、専門家への相談が近道です。
株式会社吉和の森では、Web上での集客や運用体制を検討している企業の悩みの解決につながる内容のメルマガを配信しています。お役立ち情報は無料で受け取れますので気軽に登録してみてください。
デジタルマーケティング組織体制の種類

企業の目的やリソースに合わせて専門部門型・プロジェクト横断型・外部委託型のいずれかを選択することで、連携や業務効率を高め、効果的なマーケ施策を実現できます。
専門部門型は、マーケティング専任チームを設けるためノウハウの蓄積に向いていますが、営業やITとの連携が不足しがちです。
複数部署が横断的に動くプロジェクト横断型は連携力が高まる一方、リソース管理が煩雑になることもあります。
外部委託型は最新ノウハウを取り入れやすい反面、内製化が進まずコスト増リスクが伴う点に注意しましょう。
デジタルマーケティング組織のよくある課題

デジタルマーケティング組織では「部門間の情報共有不足」「データ分析が形骸化」「担当者の業務が属人化」などの課題が起こりがちです。
これらを放置すると、連携や成果測定が滞り、重要なマーケ施策が十分に機能しなくなる恐れがあります。
そのため、根本原因を把握して早期に対策を講じることが大切です。
部門間の情報共有不足
複数の専門部署が存在すると、役割分担や報告経路が曖昧になり、営業が得た顧客情報をマーケティング部門が活用できないケースが起こりがちです。
その結果、重複アプローチによる顧客の混乱やデータ管理が複雑になり、施策に遅れが生じる可能性があります。
こうした課題を解消するには、情報共有フローを可視化し、データ共有システムを導入して運用ルールを明確化することが重要です。
部門間の連携を強化して、組織全体のパフォーマンス向上につなげましょう。定例会議やチャットツールを活用して共有タイミングを徹底すれば、顧客対応の精度も格段に高まります。
専門知識を持つ人材の不足
多くの中小企業では、マーケティングを専門とする部署がなく、他部署が兼務しているケースが目立ちます。
その結果、担当者は広範な業務を抱え、デジタルマーケティングの専門知識を学ぶ時間や余裕が確保しづらいのが実情です。
さらに、デジタル技術やユーザー行動が日々変化しているため、常に新しいノウハウをキャッチアップし続ける必要があります。
こうした課題を素早く解消するには、外注がおすすめです。専門家や外部企業の知見を取り入れることで、スキルを効率的に補完しながら、組織の成長につなげることができます。
担当者の業務が属人化
担当者が一人で運用やレポート作成を全て担うと、急な休暇や退職時に施策がストップし、蓄積されたノウハウまでも失われがちです。
また、一部の担当者に負荷が集中することで、モチベーション低下や作業精度の低下につながる恐れもあります。
こうした属人化を防ぐには、2名以上の複数体制を整え、役割やタスクを分担することがおすすめです。
万が一の離脱時にも業務が滞らないよう、日頃からドキュメント化や引き継ぎの仕組みを整備しておくと安心です。
外部リソースの活用も視野に入れることで、柔軟な体制強化が可能になります。チーム全体でマーケティングを支え合うことで、持続的な成果向上へとつなげられます。
デジタルマーケティング組織の体制づくりを成功させる7つのポイント

デジタルマーケティング組織を整える際は、経営戦略との連動やデータ活用など7つのポイントを押さえることで、新設・再編をスムーズに進められます。
具体的には下記の7つが挙げられます。
- 経営戦略と組織設計を連動させる
- 複数部門の連携を強化して組織をまとめる
- 数字やデータを活かした意思決定プロセスを確立する
- 目的・期間・予算に合わせた外部リソースの活用
- 専門人材を育成し、内製化を進める
- 企業規模に合わせたアプローチを取る
- 継続的な検証と改善を回せる仕組みを作る
施策をバラバラに進行すると連携不足やノウハウの属人化につながりがちですが、体系的なチェックリストを活用すれば、どの手順や要素が不足しているのか一目で確認できるため、組織全体のパフォーマンスを高めやすくなります。
ポイント1:経営戦略と組織設計を連動させる
デジタルマーケティングで成果を上げるには、経営戦略と組織設計を連動させることが重要です。
経営ビジョンや売上目標から逆算して部門ごとのKPIを設定し、全社で同じゴールを共有すると、リソース配分が最適化しやすくなります。
経営層と現場の指標がズレていると、施策が的外れになりがちです。方向性を一致させることで、意思決定のスピードが上がり、施策の実行力も高まります。
たとえば「売上目標→月間リード獲得数→受注率」というように階層的な指標を設け、定期的にKPI進捗をレビューすることで、部門間の連携を強化しながら効率的に成果を伸ばせます。
ポイント2:複数部門の連携を強化して組織をまとめる
マーケ、営業、ITなど各部門が情報を共有しやすい体制を整えると、重複業務やコミュニケーション不足を防げます。
部門ごとにデータが散在すると顧客対応の質が低下しやすいため、「いつ、誰が、どの情報を共有するか」をルール化することが大切です。
たとえば、部門横断の定例会議で顧客の声を共有し、チャットツールやプロジェクト管理ツールで問い合わせやタスクを一元管理すれば、施策のタイミングを逃さずにキャンペーンやサービス改善に反映できます。
こうした連携強化によって、組織全体のパフォーマンスを底上げし、成果の最大化につなげられます。
ポイント3:数字やデータを活かした意思決定プロセスを確立する
定量データに基づく施策判断を行うことで、成功率を大きく高めることができます。
担当者の経験や勘だけではなく、BIツールやアクセス解析を活用して施策ごとのROIを可視化すると、より的確な意思決定が可能です。
たとえば、Google Analyticsで集客チャネル別のCVRを計測し、高パフォーマンスのチャネルに優先的に投資することで、限られたリソースを効果的に配分できます。
さらに、BIダッシュボードを通じて経営陣と成果をリアルタイムで共有すれば、改善提案を迅速に取りまとめることができ、組織全体でデータドリブンな施策運用を推進しやすくなります。
ポイント4:目的・期間・予算に合わせた外部リソースの活用
全部を内製化するのではなく、外部の専門家や企業と連携する方針を明確にすることが重要です。
あらかじめ目的・期間・予算を整理すると、必要なスキルや業務範囲を外注しやすくなります。
たとえば、短納期のLP制作は制作会社に任せ、社内は戦略立案やデータ分析に専念するといった使い分けが効果的です。
施策ごとの優先度に応じて「誰と何を協力するか」を決め、定例MTGで成果や改善点を迅速に共有すれば、外部リソースをパートナーとして最大限に活用でき、全体のパフォーマンス向上につながります。
ポイント5:専門人材を育成し、内製化を進める
自社内にデジタルマーケティングのノウハウを蓄積し、継続的にアップデートを行う仕組みづくりは、他社と差別化できる競争優位をもたらします。
外部委託に過度に依存すると、コスト増加や社内に知見が残らないリスクがあるため、内製化を進めることが肝要です。
自社の事情を深く理解した担当者がいれば、状況に応じた施策をスピーディーに打ち出すことが可能になります。
たとえば、定期的な勉強会やオンライン研修で担当者のスキルを強化し、社内Wikiやナレッジベースを構築して成功事例や失敗事例を迅速に共有する体制を整えましょう。
これにより、知見の蓄積と活用が加速し、組織全体のデジタル施策が着実にレベルアップします。
ポイント6:企業規模に合わせたアプローチを取る
大企業と中小企業では部署数や人材リソース、決済スピードなどが大きく異なるため、求められる体制や施策の優先度も変わってきます。
大企業の場合、タスクフォースや専任チームを設けてDXを推進すると、複雑な意思決定をスムーズに進めやすくなります。
一方、中小企業は人材不足が常態化しがちなため、外部コンサルやツール活用で足りないリソースをカバーするアプローチがおすすめです。
たとえば、経営直轄のDX推進室を設けて社内外リソースを一括管理する方法や、兼任担当者でも扱えるMAツールを導入して基本ノウハウを外部研修で学ぶなど、企業規模に合わせて最適な組織体制を構築しましょう。
ポイント7:継続的な検証と改善を回せる仕組みを作る
市場やユーザーの変化に対応するためには、PDCAサイクルを絶えず回せる体制が欠かせません。
施策を打ちっぱなしにしていては効果を測れず、改善のタイミングを逃してしまいます。定期的に検証して改善を重ねることで、ノウハウが蓄積され、長期的な成果につながるのです。
たとえばA/Bテストを活用してLPやメール配信のクリエイティブを随時最適化し、月次レビュー会で前月の施策を振り返りながら翌月の改善策を即座に反映する仕組みを整えましょう。
こうした継続的な検証と改善を実行できる体制こそが、競争力の高いデジタルマーケティング組織を築くカギです。
理想の体制を目指すなら、専門家への相談が近道ですので、ぜひ自社サービスへの問い合わせをご検討ください。
よくある組織体制の失敗パターンとその対処法

デジタルマーケティング組織で頻発する失敗として、「責任範囲のあいまい化」「データ活用が進まない」「経営層と現場の温度差が大きい」といったパターンが挙げられます。
誰が何を担当するか明確にしていないと施策が遅れ、成果も不透明になりがちです。
また、データを集めるだけで分析や活用の仕組みがなければ、最終的な成果に結びつかない可能性があります。
さらに、経営陣と現場の視点が大きく異なると、意思決定のズレやモチベーション低下を招きやすいです。
対策として、部門長を中心に職務分掌表を作成し、BIツールや定例会議で数値を共有しながら、経営層と現場が定期ミーティングを行い、互いの状況をすり合わせることが重要です。
理想のデジタルマーケティング体制を叶えるなら「専門家への相談」がおすすめ!

デジタルマーケティング組織を構築するうえでは、経営戦略との連動や部門間の連携、データドリブンの意思決定、人材育成、外部リソースの活用、企業規模に合った施策の選択、そしてPDCAサイクルの継続が重要です。
これらを全て押さえておくと、企業全体がデジタル施策にスムーズに適応し、業績アップに直結しやすくなります。
また、新技術や市場の変化に柔軟に対応でき、長期的な競争力を維持しやすいのも大きな利点です。まずは現状分析とKPI設定から始め、必要に応じて組織変更やツール導入を計画的に進めましょう。
定期的なレビューと改善サイクルを回すことで、徐々に組織力を高められます。理想の体制を構築する近道として、専門家への相談もぜひご検討ください。
株式会社吉和の森では、Web上での集客や運用体制を検討している企業の悩みの解決につながる内容のメルマガを配信しています。お役立ち情報は無料で受け取れますので気軽に登録してみてください。


 株式会社 吉和の森
株式会社 吉和の森