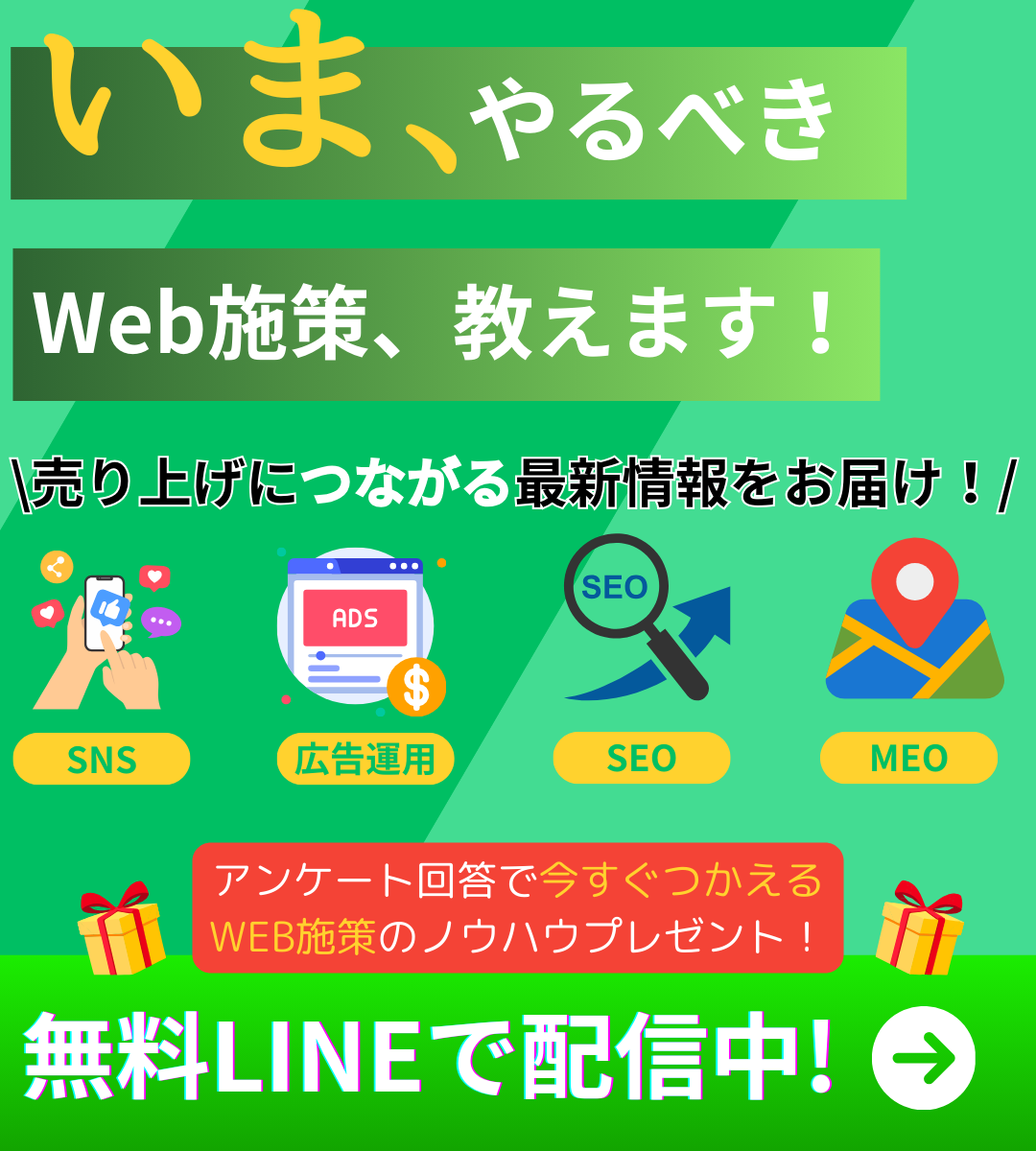生成AIは文章や画像を自動で作れる便利な技術で、ビジネスの現場でも広く使われ始めています。
ただし、誤情報の拡散や詐欺への悪用、著作権侵害といったリスクも存在します。
安全に使うには、危険性を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。
本記事では、ビジネスパーソンが知っておくべき生成AIのリスクと安全な使い方を、中学生にもわかる言葉でわかりやすく解説します。

『デジタル・マーケティング超入門』の著者が
「Web集客の仕組み」で売上を創ります
はじめに:話題の生成AIの便利さの裏に潜む「危険性」とは?
まずは、生成AIについての概要をメリット・デメリットの両面から解説します。
難しい言葉をできるだけ使わずに解説するので、生成AI初心者の方もご安心ください。
生成AIとは「大量のデータを学習し、その知識をもとに新しいコンテンツを自動で作り出すAI技術」
生成AIとは「大量のデータを学習し、新しい文章や画像を自動で作成するAI技術」のことです。
たとえば「〇〇について教えて」と聞けば答えを返し、「青空の風景を描いて」と伝えれば絵も描いてくれます。
難しい操作は不要で、誰でも使えるのが大きな魅力です。
その背景には、人間の自然言語(話す言葉)を理解する能力に長けていることが要因として挙げられます。
文章作成や企画書、デザイン、プログラム作りなど、仕事の効率を上げる場面で多く使われています。
生成AIについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
生成AIは便利だが、危険性もある
生成AIは便利な技術ですが、使い方を誤ると重大なトラブルを引き起こす可能性があります。
たとえば、誤った情報を提供する点はAI利用時に気をつけたいポイントです。
AIは学んだ内容をもとに文章を作りますが、その元が間違っていると、もっともらしいけれど間違った内容を出すことがあります。AIを使って情報収集する際は、ファクトチェックを怠らずにしましょう。
また、著作権問題も深刻です。AIが作った画像や文章が、他人の作品に似すぎていると、知らないうちに著作権を侵害してしまうこともあります。
このように、便利なAIだからこそ、正しい知識と使い方が欠かせません。
ビジネスパーソンが知っておくべき生成AIの主な危険性・リスク5選

生成AIは業務効率を大きく高めてくれますが、その一方で無視できないリスクも多く存在します。
特に、日々の業務判断や顧客対応などに関わるビジネスパーソンにとっては、単なる「便利なツール」として片付けられない問題が山積しています。
- ハルシネーションが起こる
- 情報漏洩する恐れがある
- 著作権を侵害してしまう
- 詐欺や攻撃に悪用される
- AIの偏った考え・バイアスに影響される
ひとつずつ見ていきましょう。
リスク①:ハルシネーションが起こる
生成AIは、まるで正しい情報のように事実と異なる内容を出力することがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。
AIは多くの情報を学習しますが、その中には誤った内容も含まれており、必ずしも正確とは限りません。
実際、GoogleのBardが誤った情報を提示したことで親会社の株価が大きく下落した事例もあります。
参照元:https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN2UI1TU/
ビジネスでは、ひとつの誤情報が意思決定のミスや取引先との信頼関係の崩壊につながる恐れがあります。
対策としては、AIの回答をそのまま信じないことです。
80%くらいで信用しながらも、以下のようなチェックをしましょう。
- 出典付きの回答を求める
- 複数の情報源で確認する
- 社内でダブルチェックする体制を整える など
リスク②:情報漏洩する恐れがある
生成AIに社内の機密情報を入力すると、そのデータが外部に漏れる危険があります。
AIは一部のサービスで入力内容を学習に利用するため、知らないうちに社外へ情報が拡散することもあります。
実際、サムスン電子では開発中のソースコードをChatGPTに入力した結果、情報が外部に漏れ、社内でのAI利用が全面禁止になった事例があります。
参照元:https://forbesjapan.com/articles/detail/62905
このような事態を未然に防ぐには「機密情報の入力禁止」を徹底し、信頼できる閉じた環境(例:Azure OpenAI)での利用や、社内ポリシーの整備が欠かせません。
リスク③:著作権を侵害してしまう
生成AIは、既存の作品に似たコンテンツを出力することがあります。意図せず著作権を侵害してしまうと、法的な問題に発展する恐れがあります。
たとえば、中国ではAIがウルトラマン風の画像を生成し、著作権侵害と判断され有罪となった事例が報道されました。
参照元:https://www.yomiuri.co.jp/culture/subcul/20240415-OYT1T50069/
企業がAIで作った画像や文章を使った結果、訴訟や損害賠償に発展すれば、信用を大きく損なうことになります。
対策としては、以下が挙げられます。
- プロンプトの工夫
- AI生成物への手直し
- 出力内容の類似チェック
- 社内教育 など
リスク④:詐欺や攻撃に悪用される
生成AIは、顔や声を精巧に再現できるディープフェイク技術と組み合わせることで、詐欺に悪用されるリスクがあります。
香港では、ビデオ通話で上司に偽装したAIを使い、企業から約25億円を騙し取る事件が実際に起こりました。
参照元:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81297770Q4A610C2FF8000/
このような詐欺に巻き込まれると、金銭的な被害だけでなく、顧客や取引先からの信頼を失うことになります。
高額取引時の本人確認や、怪しい連絡への多段階確認、従業員への注意喚起が必須です。
生成AIを使った詐欺の実情について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
リスク⑤:AIの偏った考え・バイアスに影響される
AIは学習するデータに偏りがあると、差別的な発言や不公平な判断をするおそれがあります。これを「AIバイアス」と呼びます。
たとえば、採用で特定の性別や年齢ばかりを優先するような結果が出ることがあります。これは、AIが過去の偏ったデータを学習してしまったためです。
こうした偏見が業務に影響すると、不当な判断や訴訟のリスク、企業イメージの悪化につながります。公正性を保つには、多様なデータによる学習、判断の監査、倫理ガイドラインの整備と教育が必要です。
生成AIの危険性を回避!ビジネスで安全に使うための5つの対策

生成AIを業務に取り入れる企業が増える一方で、「何を注意すべきか分からない」という声も少なくありません。
便利なツールだからこそ、正しく使わなければリスクに巻き込まれる可能性があります。
ここでは、実務で生成AIを安全に使うための、すぐに実践できる5つの対策をわかりやすく紹介します。
- AIの出力する答えを鵜呑みにしない
- 入力してはいけない情報のルールを決める
- 著作権を意識した使い方を心がける
- 生成AIを使用した詐欺があることを認知する
- 自分の頭で考える習慣をつける
それぞれ詳しく解説します。
対策①:AIの出力する答えを鵜呑みにしない
生成AIは一見正しそうな答えを出しても、内容が事実とは限りません。
これは「ガベージイン・ガベージアウト(GIGO)」という考え方が関係しています。質の低い情報を学習すれば、当然出力も不正確になるのです。
AIが「これは正しい」と言っていても、その情報が古かったり、誤解を含むこともあります。
特にビジネスで活用する際は、内容を慎重に検証することが大切です。
リスクを抑えるためには、人の目で情報をチェックする習慣を持つようにしましょう。
対策②:入力してはいけない情報のルールを決める
生成AIは便利な反面、入力した情報を学習に使うケースもあります。
そこに機密情報や個人情報が含まれていると、第三者に漏れてしまうリスクが高まります。
たとえば、社内の顧客名簿や取引先情報、病歴や住所などをうっかり入力してしまうと、大きなリスクにつながります。
実際、情報漏洩によりAIの使用が社内で禁止された企業もあります。
こうした事態を防ぐには、「入力禁止の情報」を明確にルール化し、全社員に徹底して共有する必要があります。
対策③:著作権を意識した使い方を心がける
生成AIは、知らないうちに既存の作品に似たコンテンツを作ってしまうことがあります。その結果、著作権を侵害してしまうおそれがあります。
特に気をつけたいのは、画像や音声を生成する場合です。自分が作ったつもりでも、他人の作品に酷似していると訴えられる可能性があります。
対策としては、以下のような取り組みが挙げられます。
- 生成物の使用前に類似コンテンツがないかを確認する
- 出所を明記する
- 必要があれば使用許諾を取る など
対策④:生成AIを使用した詐欺があることを認知する
最近では、生成AIを使った詐欺やなりすましの被害が増えています。
特にディープフェイクを使った「偽の音声や映像」で、上司や取引先を装った詐欺が横行しています。
こうした詐欺に騙されないためには、「AIによる詐欺は現実にある」とまず理解することが第一歩です。
次に、防止ツールや本人確認の仕組みを導入し、不審なやり取りに備える必要があります。
従業員に向けた教育や、定期的な注意喚起も欠かせません。
最近は「偽ChatGPT」のアプリも急増中。利用者側のITリテラシーを高めて、安全に生成AIを活用しましょう。
対策⑤:自分の頭で考える習慣をつける
生成AIはとても便利なツールですが、頼りすぎると「考える力」が鈍ってしまうおそれがあります。
特にビジネスでは、最終的な判断を人が下す必要があります。
AIの回答をそのまま信じず、「本当に正しいのか?」「他の見方はないか?」と常に考える習慣を持ちましょう。
そのためには、自分の頭で考える習慣をつけることが大切です。AIはあくまで補助的なツールとして使い、自分の判断力を大切にすることが重要です。
生成AIリスク、放置は禁物! 今すぐ始めるべき「社内対策」

生成AIのリスクは「知っているだけ」では不十分です。
中小企業や情報管理が得意でない組織では、ルールの整備不足がトラブルの元になります。
ここでは、今すぐ実践できる3つの対策を紹介します。
- 利用ルール・ガイドラインの策定と周知徹底
- 従業員向け研修の実施とリテラシー向上
- 入力情報の管理とチェック体制の構築
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 利用ルール・ガイドラインの策定と周知徹底
生成AIを安全に活用するには、社内で明確なルールを定め、それを全員に共有することが基本です。
特に、機密情報の入力禁止や不正操作(プロンプトインジェクション)への対策は欠かせません。
ガイドラインには以下のような項目を具体的に盛り込みましょう。
・使用を許可するAIツールの一覧
・入力してよい情報と禁止情報の区別
・出力物の確認・修正方法
東京都のように、情報をA・B・Cの機密レベルに分けて管理する体制を整えれば、運用ミスを防げます。
責任者を明確にして、継続的に運用・改善する姿勢が大切です。
2. 従業員向け研修の実施とリテラシー向上
生成AIを社内で安全に使うには、使う人のリテラシー(知識と意識)がカギになります。そこで効果的なのが、実践的な研修の導入です。
たとえば、TISではプロンプト(指示文)の作り方を体験形式で学ばせることで、従業員の不安を解消しています。また、AIリテラシー診断や段階的な学習カリキュラムを使って、理解度を“見える化”するのも有効です。
「ハルシネーション」などAIの誤り事例を使った研修は、検証力や判断力を高めるのに効果的です。
3. 入力情報の管理とチェック体制の構築
社内で生成AIを活用する際には、「誰が・何を・どこまで入力しているか」を明確に管理する体制が必要です。
たとえば、安全性の高いAzure OpenAI Serviceを使えば、アクセス制限やデータの暗号化が行えます。また、社内ドキュメントをAIの情報源に活用するRAG技術を使えば、社外に情報が漏れるリスクも減らせます。
AIの出力や操作履歴を定期的にチェックすれば、不正利用の早期発見につながります。
安全な生成AIツールを見極めるには? 導入前に確認したいポイント
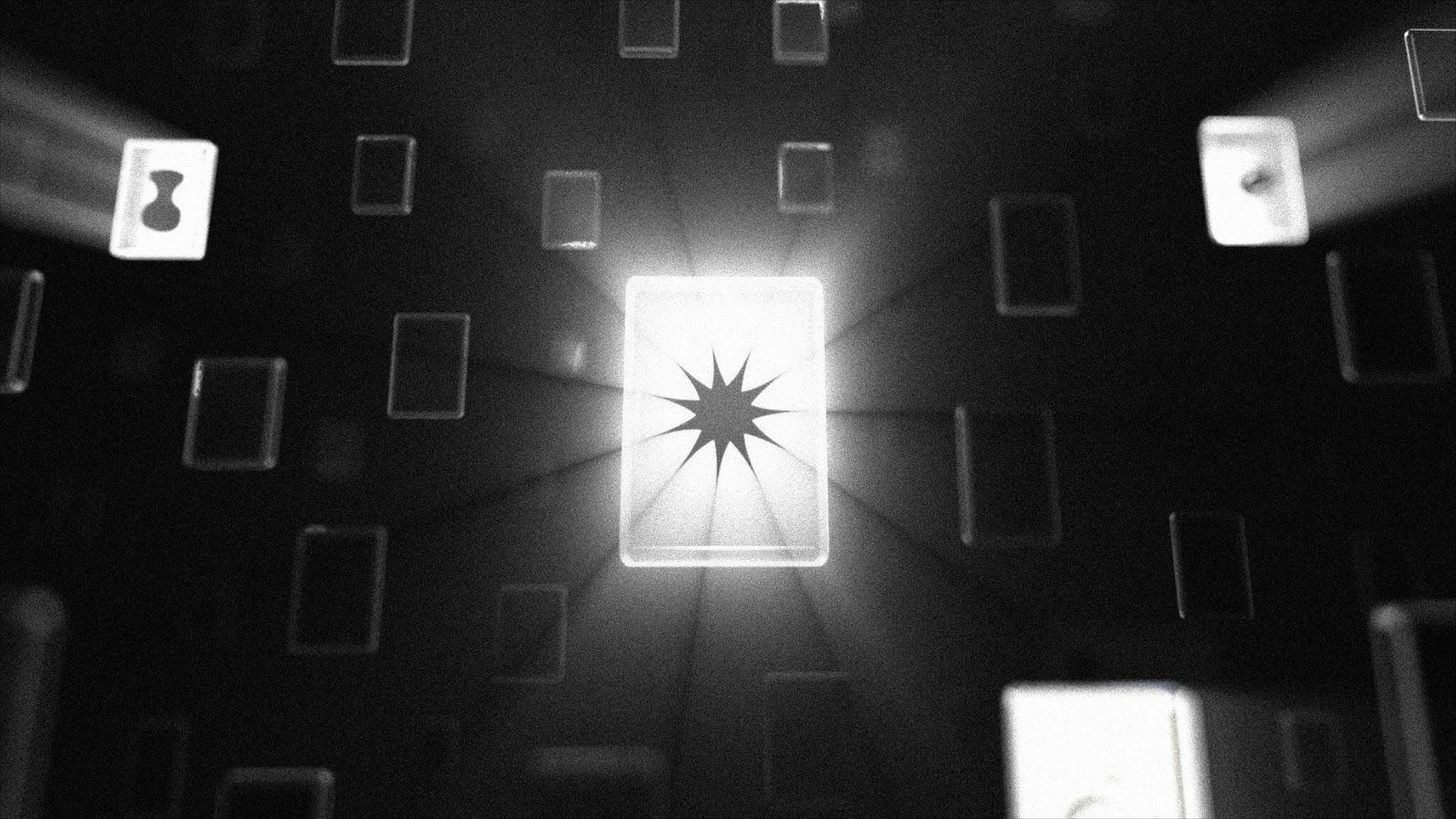
生成AIには多くのツールがあり、どれを選べばよいか迷う人も少なくありません。
実際、セキュリティ対策が不十分なツールを選ぶと、情報漏洩やトラブルの原因になることもあります。
ここでは、生成AIを導入する前に確認すべき3つのポイントを、具体的に解説します。
- 提供元企業の信頼性と実績を確認する
- セキュリティ対策・管理機能の有無をチェックする
- データ取り扱い・プライバシーポリシーを読み解く
ひとつずつ見ていきましょう。
ポイント①:提供元企業の信頼性と実績を確認する
生成AIツールを選ぶ際は、まず提供元企業が信頼できるかを見極めましょう。業界での評判やレビューを確認し、過去にトラブルがないかを調べることが大切です。
導入事例を公開している企業であれば、どのような課題をどう解決したのかを知ることができ、導入後のイメージも明確になります。
さらに、開発チームの技術力や、AIに関する研究実績があるかも判断材料になります。
ポイント②:セキュリティ対策・管理機能の有無をチェックする
生成AIを安心して使うには、セキュリティ対策がしっかりしているかを確認する必要があります。
通信の暗号化やアクセス制御(RBAC)の有無は、特に重要なチェック項目です。
加えて、リアルタイムでの脅威検知や自動対応機能があると、サイバー攻撃の被害を最小限に抑えられます。
「定期的な脆弱性診断や監査が実施されているか」「セキュリティレポートの提供有無」も確認しましょう。
ポイント③:データ取り扱い・プライバシーポリシーを読み解く
ツールがユーザーのデータをどう扱うかも、必ず確認すべきポイントです。どんなデータを収集し、それを何に使うのか明記されているかをチェックしましょう。
特にGDPRや国内の個人情報保護法に準拠しているかどうかは、企業としての信頼性に関わります。
さらに、保存方法やセキュリティ対策、ユーザー自身がデータを管理できる仕組みがあるかも確認しましょう。
まとめ:生成AIの危険性を理解し、賢く付き合っていこう
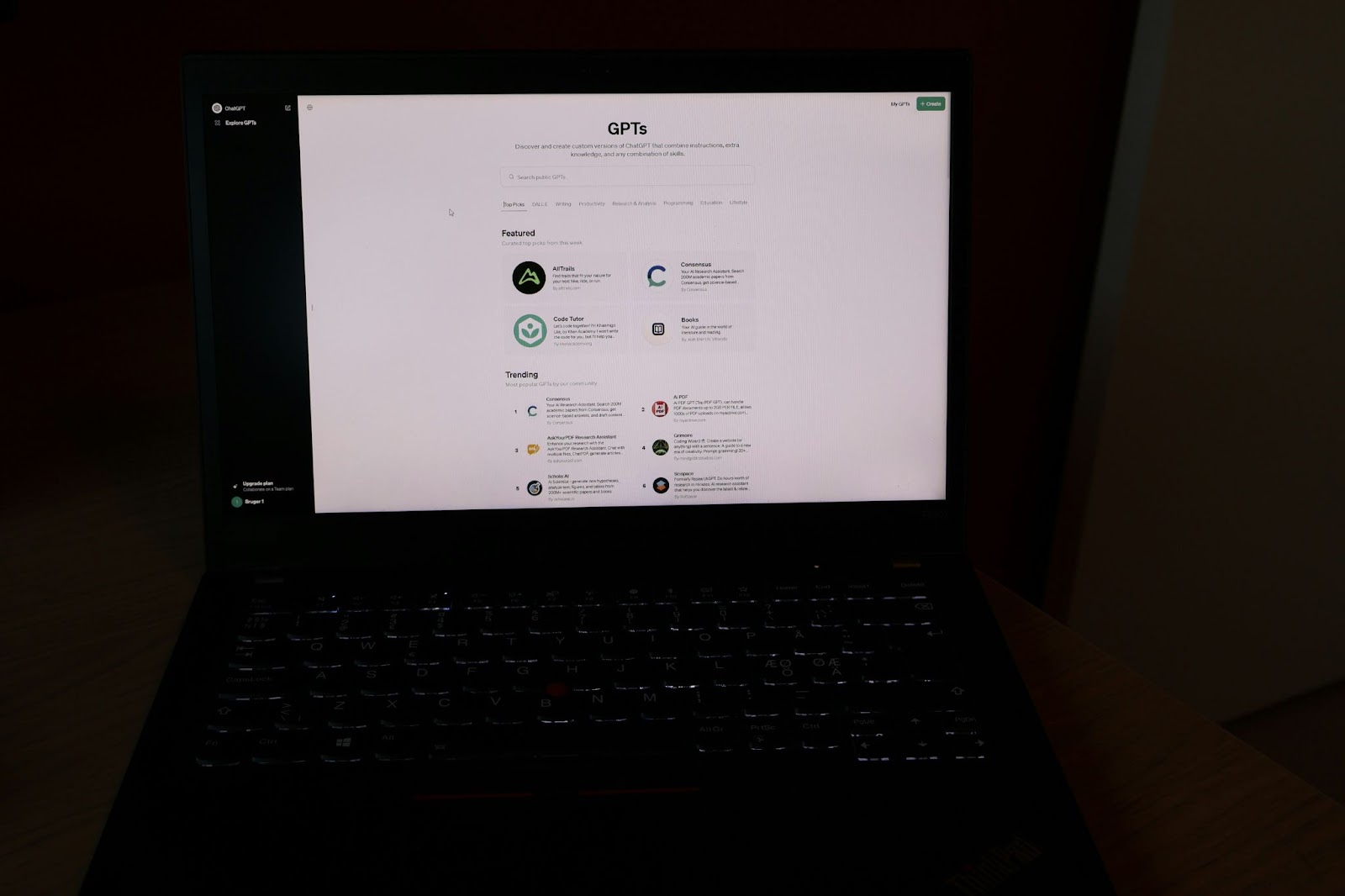
生成AIは、うまく使えば業務効率を大きく高めてくれる強力なツールです。
しかし、誤情報の拡散や情報漏洩、著作権侵害など、さまざまなリスクがあることも事実です。
だからこそ、便利さだけでなく、正しい知識とルールをもとに活用することが重要です。
本記事で紹介したリスクと対策を参考に、安心して使える環境を整えましょう。
AIと共に生きる時代には、自分で考え、前向きに使いこなす姿勢が成功のカギになります。
吉和の森では生成AIに関するどんな質問にも回答させていただきます。
30分間の無料お問い合わせでお気軽にご相談ください。

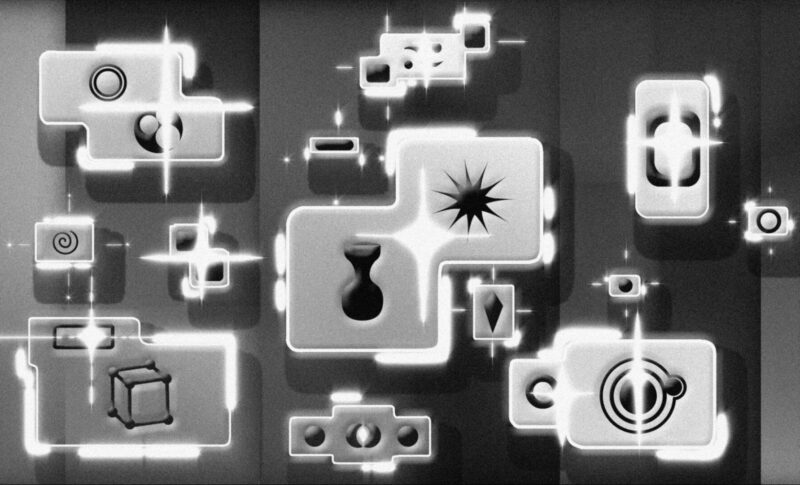




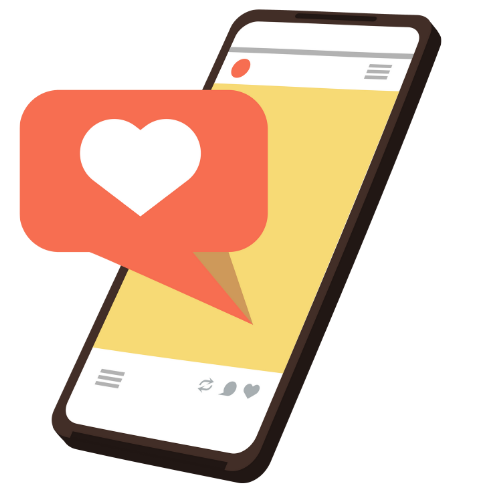
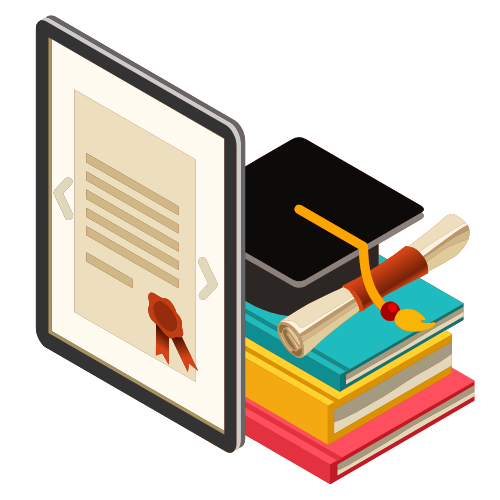
 株式会社 吉和の森
株式会社 吉和の森