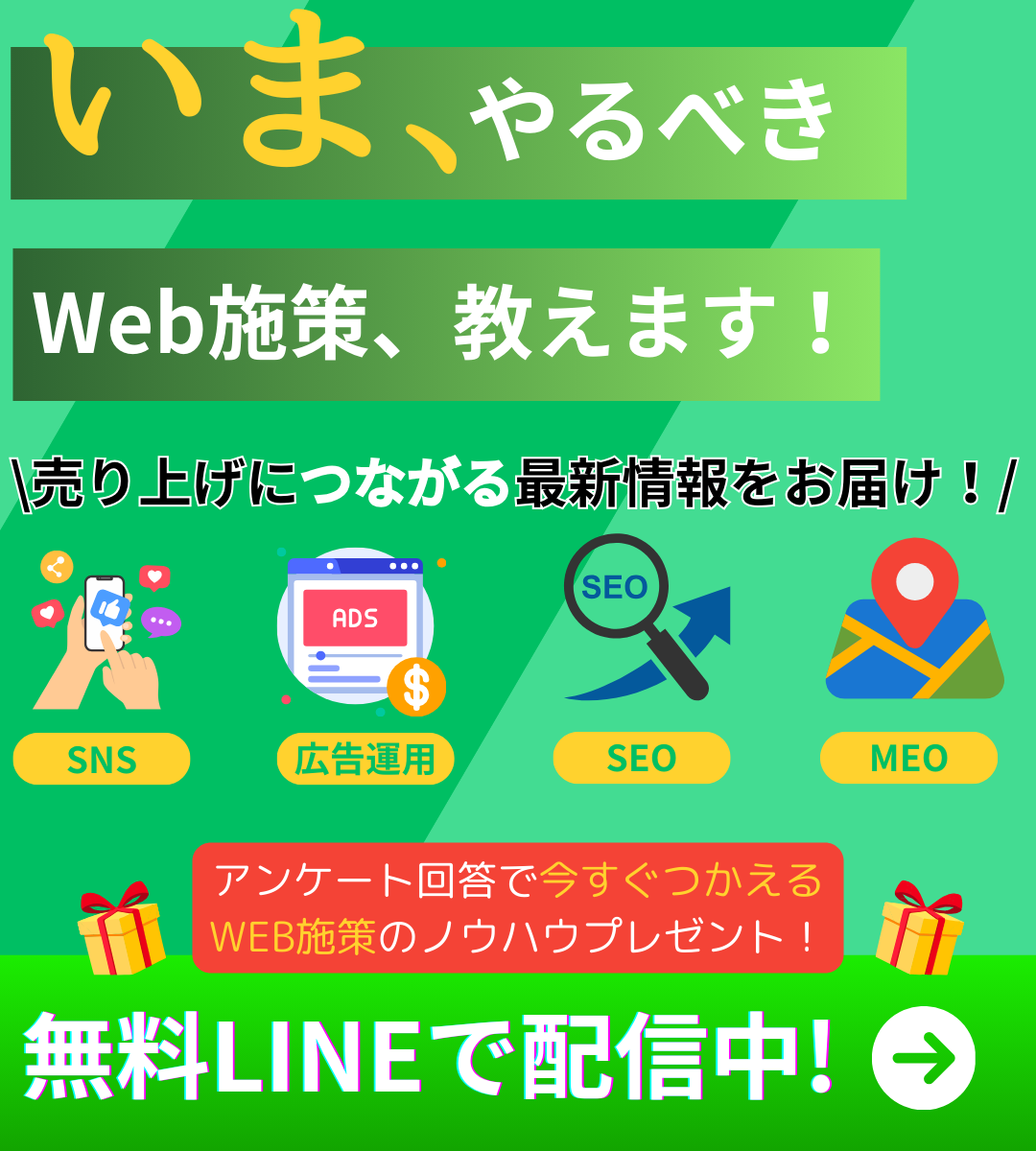「Xの企業アカウントを運用したいけれど、人手も時間も足りない…」そんな悩みを抱えていませんか?
競合他社がXで顧客との接点を増やしファンを育てる中、何もしなければ機会損失は広がる一方です。
この記事を読めば、限られたリソースでも成果を出せる、X企業アカウント運用の具体的なロードマップがわかります。
本記事では、アカウント開設の基本から日々の投稿ネタ、炎上対策まで、担当者1人でも明日から実践できるノウハウを紹介します。
なぜ今、X(旧Twitter)の企業アカウントが重要なのか?メリット・デメリットを解説
Xは「リアルタイム性」と「拡散力」を強みとし、企業の発信と顧客対話の中核を担うSNSです。
短文で発信でき、投稿コストも低いため、速報性のある情報発信が可能です。今後の企業マーケティングにおいて、X 企業アカウントの活用は欠かせません。
企業がXをするメリット:低コストでの認知拡大と顧客との関係構築
最大のメリットは、低コストでの「認知拡大」です。リポスト文化により、投稿が共感を呼べば、広告費をかけずに自然に拡散されます。トレンドに乗れば、少ない労力で数万インプレッションも可能です。
また、「中の人」の個性を活かすことで、親しみのあるブランディングやファンとの交流を実現しやすいのも特徴です。ユーザーのリアルな声を即時に収集でき、製品改善や顧客満足度の向上にも直結します。
企業がXをするデメリット:炎上リスクと継続的な運用の手間
最大の注意点は「炎上リスク」です。即時性が高い分、誤情報や不適切な投稿が瞬時に拡散され、ブランドイメージを損ねる危険があります。トレンドの変化も早く、定期投稿やリアルタイム対応が求められるため、担当者の負担が増大しやすい側面もあります。
対策として、明確な「発信ルール(ガイドライン)」を設けることが不可欠です。一貫した口調や対応スピードを保つことが信頼構築の鍵となります。成果が出るまで時間はかかりますが、ルール整備と改善を行えば、炎上を防ぎつつブランド価値を高められます。

『デジタル・マーケティング超入門』の著者が
「Web集客の仕組み」で売上を創ります
担当者1人でもOK!Xアカウント開設から運用開始までの5ステップ

担当者が1人でも、これから紹介する5つのステップを踏めば、着実にX企業アカウントを始められます。重要なのは、運用方針という「土台」を作ることです。
Step 1:目的とターゲット(誰に、何を伝えたいか)を明確にする
Xを始める目的とターゲットを決めるのが、最も重要なステップです。
- 何のために運用するのか(目的)
- 誰に届けたいのか(ターゲット)
目的・ターゲットの例としては、「新製品PR」「採用強化」「顧客サポート」 ターゲット例:「30代女性、子育て中」「都内勤務の20代営業職」などが挙げられます。
ターゲットを絞れば、刺さる投稿内容が設計できます。この段階で運用方針やKPI(目標数値)を決めると、途中で迷走しなくなります。
Step 2:親しみやすい「中の人」のキャラクターを設定する
Xで伸びている企業アカウントの多くは、企業ロゴで淡々と情報発信するのではなく、「中の人」の人格設定をうまくやっていることが多いです。
ブランドイメージに合わせ、「フレンドリーで明るい」か「専門的で誠実」かなど、トーンを設定しましょう。「公式スタッフのササキが担当しています」といった形で統一感を出しましょう。
親しみやすさでフォロワーからリプライ(返信)をもらいやすくなり、交流が活性化します。“人間味のあるアカウント”を作ることが継続のコツです。
Step 3:プロフィールとヘッダー画像を設定する(無料ツールでOK)
プロフィールは、アカウントの「顔」となる部分です。アイコンには企業ロゴ、ヘッダー画像には理念が伝わるものなどを設定します。デザインは「Canva」などの無料ツールで十分作成可能です。
プロフィール文には160文字以内で以下のことを明確に書きましょう。
- 「どんな会社か」
- 「どんな情報を発信しているか」
- 「フォローするメリット」
公式サイトURLも忘れずに掲載し、信頼感を確保します。
Step 4:最初の投稿をしてみる(投稿テンプレート付き)
設定が完了したら、いよいよ最初の投稿です。自然体かつ温かみのある文面を意識しましょう。
【テンプレート例】
「はじめまして!〇〇株式会社の公式Xアカウントです。 これから〇〇の最新情報や、役立つ豆知識などを発信していきます! どうぞよろしくお願いします!」
投稿ネタは「自己紹介+発信方針」「キャンペーン告知」などがおすすめです。写真や動画を添えると目を引きます。投稿後は、寄せられたリプライや「いいね」に積極的に反応し、最初のファンづくりを意識することが大切です。
Step 5:業界の有名アカウントを10個フォローする
運用初期は、まず情報収集のアンテナを広げることが大切です。関連業界の有名アカウントや競合他社などを10アカウント程度フォローしましょう。
これにより、業界トレンドを把握し、自社の発信テーマのヒントを得られます。相互フォローやリポストの機会が増え、初期の拡散効果を得やすくなります。「企業」「メディア」「専門家」をバランスよく選定し、情報収集と交流を図りましょう。
毎日のXの投稿内容はどうする?ネタ切れを防ぐ3つのアイデア
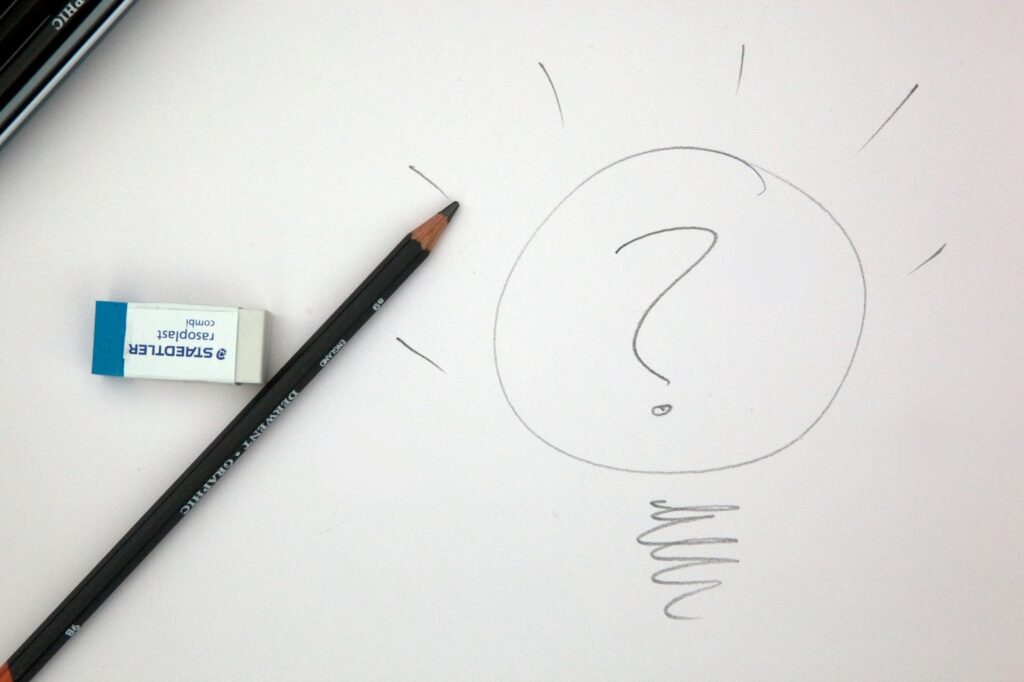
次にぶつかる壁が「投稿ネタ切れ」です。ここでは、担当者1人でもネタ切れを防ぎ、フォロワーに喜ばれる投稿を続ける3つのアイデアを紹介します。
自社の商品・サービスの裏側や豆知識
フォロワーは「普段見られない裏側」に興味を持ちます。これを発信することで、信頼感と親近感を高められます。
- 農業企業が栽培の工夫を紹介
- 家電メーカーが製品の隠れ機能を発信 など
投稿には写真や短い動画を添え、専門用語はかんたんな言葉に置き換えましょう。「技術者インタビュー」「開発ストーリー」のシリーズ化も有効です。裏側紹介は、ブランドの“誠実さ”や“人の温かみ”を伝える絶好の手段です。
業界ニュースやトレンドへの専門家としてのコメント
業界ニュースやトレンドに対し、「専門家としてのコメント」を発信し、専門性と信頼性をアピールします。
重要なのは、単なる情報の転載ではなく、「当社が考えるポイントは〇〇です」といった独自の洞察を加えること。週1〜2回が目安です。情報源を明示し、フォロワーにとって“頼れる存在”として認識されましょう。
フォロワーとのコミュニケーション(質問箱、アンケート機能の活用)
Xの「双方向性」を活かし、フォロワーを巻き込む投稿も優れたネタになります。例えば、アンケート機能を使い、「次期モデルに追加してほしい機能は?」と意見を募集します。
また、「質問箱」で相談を受け付け、その回答を共有することで、他のフォロワーの疑問も解決でき、顧客満足度の向上につながります。UGCを紹介するのも効果的です。こうした仕組みで投稿負担を減らしつつ、エンゲージメントを高められます。
参考にしたい!中小企業のXアカウント成功事例3選

限られたリソースの中で工夫し、X企業アカウントの運用に成功している中小企業の事例を3つ紹介します。自社に応用できるヒントを見つけてください。
お〜いお茶くん|伊藤園
「お〜いお茶くん【公式】」アカウントは、ユーザーの参加ハードルを極端に下げるUGC施策が非常に参考になります。人気商品を使った面白いコンテンツを多数発信。
おっちょこちょ〜い、お茶
(開けるときに勢い良すぎました😭)#お〜いお茶 pic.twitter.com/BqLM9HnmI1— お〜いお茶くん【公式】 (@oiochakun) October 8, 2025
フジドリームエアラインズ 【公式】@SNS担当が運用中
「フジドリームエアラインズ 【公式】」では、航空会社ならではの飛行機の写真などを高画質&鮮明に撮影。
こんばんは、FDAです👋
少し前の名古屋空港の早朝で撮影された #JA14FJ ワインレッド号です🍷
夜が明けて、幻想的な光景を #FDA整備士 が捉えてくれました📸
おやすみなさい💤 pic.twitter.com/Dz5baxlVmV— フジドリームエアラインズ【公式】┃FUJI DREAM AIRLINES✈️ (@FDA_fujidream) October 8, 2025
飛行機好きの方などから「かっこいい」などのリプを自然に引き出しているため、自社の強みをうまく活用している一例として参考にしましょう。
丸亀製麺【公式】
丸亀製麺【公式】ではキャンペーン企画を多数打ち出し、フォローや引用ポストを促しています。
/
地域の食文化や食材を活かしたご当地企画🗾✨#わがまちうどん47 クイズ💡
第2問目🎉
\
ヒントも参考にしてみて下さい!
抽選で100名様に #わがまちうどん47 に使える500円引きクーポン🎁
①@UdonMarugameをフォロー
②#わがまちうどん47 をつけクイズの回答を引用ポスト
③当選者のみ後日DM pic.twitter.com/jM99WGtlJ2— 丸亀製麺【公式】 (@UdonMarugame) October 18, 2025
プレゼント企画などはフォロワーを増やすのに即効性があるため、伸び悩んでいる方はぜひ実践してみてください。
まとめ

本記事では、中小企業がX 企業アカウントを運用するメリットから、担当者1人でも始められる開設ステップ、投稿アイデア、成功事例までを解説しました。
Xは、低コストで認知を拡大し、顧客と直接的な関係を築ける、中小企業にこそ最適なツールです。
「炎上が怖い」「時間がない」とためらう前に、まずは「目的設定」と「キャラクターづくり」から始めてみませんか。その小さな一歩が、未来のファン獲得とビジネス成長につながります。






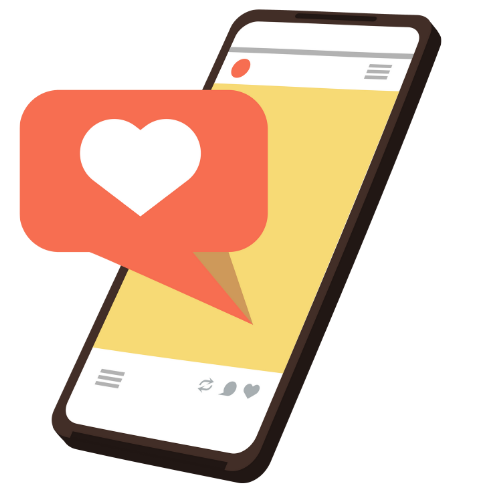
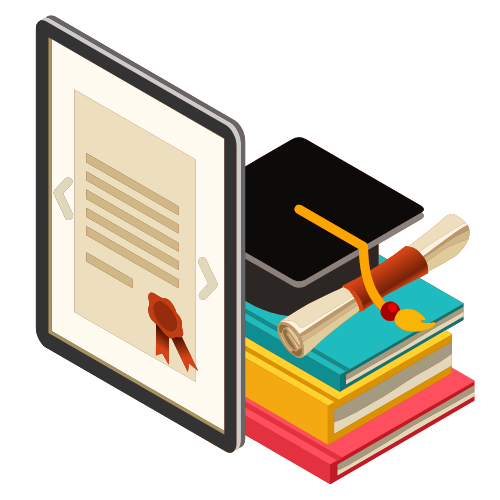
 株式会社 吉和の森
株式会社 吉和の森