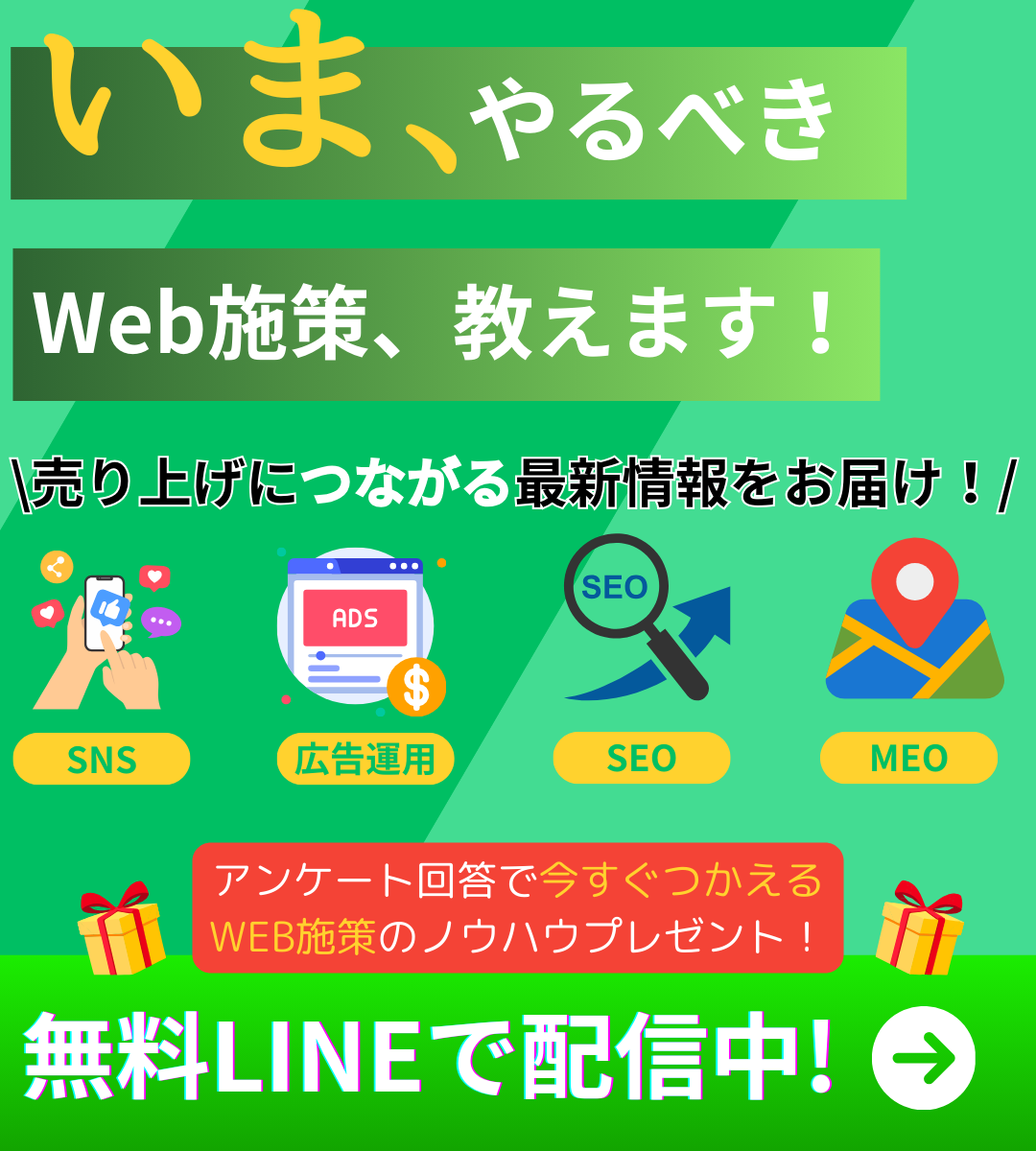近年、生成AIを悪用した詐欺が急増していることをご存じですか?
AIで作られた偽の音声や動画を使い、家族や上司になりすまして金銭を騙し取るケースが増えています。
本物と見分けがつかないほど精巧な詐欺が増えており、知識がないと騙されるリスクが高まっているのです。
この記事では、生成AI詐欺の手口と被害事例を詳しく解説します。
被害を防ぐ対策も紹介するので、以下の悩みがある方はぜひ最後までご覧ください。
- AIを安全に活用したい
- AI詐欺に引っかかりたくない
- 身の回りの人にAIの危険性を伝えたい
ではまず、生成AIとは何かについて簡単に見ていきましょう。
はじめに:生成AIとは?
生成AIとは、大量のデータを学習し、そのパターンを基に新しいコンテンツを作成する人工知能の技術です。
文章・画像・音声・動画・音楽など、さまざまなコンテンツを自動生成できるのが特徴です。
生成AIは、簡単な指示(プロンプト)を入力するだけで、高品質なコンテンツを作れます。
また、特別な技術知識がなくても使うことが可能です。そのため、ビジネスだけでなく、趣味や学習の場面でも広く活用されています。
こちらの記事では生成AIについてより詳しく解説しています。「ChatGPTと生成AIの違いを知りたい」という方は参考にしてください。
しかし、こうした便利な技術を悪用した「生成AIを使った詐欺」が増えていることも事実です。
次の章では、具体的な詐欺の手口を解説していきます。
生成AIを使った詐欺とは?主な4つの種類を解説

AI技術の進化により、詐欺の手口も巧妙化しています。
特に、生成AIを悪用した詐欺は本物と見分けがつきにくいため、気づいたときにはすでに被害に遭っているケースも少なくありません。
ここでは、代表的な4つの手口を紹介します。
- クローン音声詐欺(AIで作った偽の声)
- AIフィッシング詐欺(本物そっくりのメールやメッセージ)
- ディープフェイク詐欺(偽の動画や画像を悪用)
- 「AI副業で稼げる」と騙す詐欺
ひとつずつ見ていきましょう。
種類①:クローン音声詐欺(AIで作った偽の声)
「クローン音声詐欺」とは、従来の「オレオレ詐欺」を進化させた手法で、AIを使って家族や会社の上司の声をそっくりに再現し、金銭を騙し取る手口です。
誰しも、電話で「事故に遭った」「助けて」と言われれば、慌てて信じてしまうもの。
最近の実例として、後ほど詳しく紹介する香港の企業のケースのように、財務担当者がAIで再現された社長の声に騙され、大金を送金する事件が発生しています。
声だけでは本物かどうか判断するのが難しく、電話でのやりとりだけを信じるのは危険です。
種類②:AIフィッシング詐欺(本物そっくりのメールやメッセージ)
「AIフィッシング詐欺」はAIを活用した最先端のフィッシング詐欺のことです。
近年、悪徳業者はAIを使って、ターゲットに合わせた文体のメッセージを作成して詐欺を働いています。
例えば、銀行や役所を装ったメールで「あなたの口座に問題があります」と通知し、偽のサイトに誘導。そこでパスワードや個人情報を入力させ、盗み取る手口です。
AIが書いたメールの精度が上がり、本物そっくりの文章を生成できるため、違和感なく騙されるケースが増えています。
種類③:ディープフェイク詐欺(偽の動画や画像を悪用)
「ディープフェイク詐欺」とは、AIを使って実在する人物の顔や声を合成した偽の動画や画像を利用する詐欺です。
例えば、有名人が「この投資法で私も成功しました!」と宣伝する偽の映像を作成し、信頼性を装います。
それを信じて申し込んだ人が、大金を騙し取られるケースが増えているんです。
「そんなことで騙されるの?」と思われるかもしれませんが、AIの生成する動画・音声のクオリティは非常に上がっています。
本物と見分けがつかなくなっているため、見るだけ・聞くだけで真実かどうかを判断できません。
種類④:「AI副業で稼げる」と騙す詐欺
「AIを使えば誰でも簡単に稼げる!」と宣伝し、最初に高額なツール代や講座料を支払わせる手口の詐欺も急増しています。
情報商材ビジネスなどで「AI×〇〇」を絡めて宣伝するケースが増えているのが現状です。
「スマホで簡単にできる」「特別なスキルは不要」といった魅力的な言葉で誘いますが、実際には収益が出ないことがほとんど。
SNSやネット広告で頻繁に見かけますが、「すぐに稼げる」「誰でも成功できる」といった話には要注意です。
見抜くべき危険信号?生成AI詐欺のよくある手口3つ

生成AIを悪用した詐欺は、さまざまな形で私たちの身近に潜んでいます。
ここでは、特に多い手口を3つ紹介します。
手口①:AIが自動返信する偽のチャットサポート
詐欺師が本物そっくりの企業のウェブサイトを作り、AIを使ったチャットサポートを導入します。
具体的には、詐欺師が偽の銀行や通販サイトを作成し、そこにAIチャットボットを導入します。問い合わせに対してAIが自然に応答するため、被害者は本物のサポートと思い込み、個人情報やクレジットカード情報を提供してしまうという手口です。
「商品が届かない」と相談すると「追加の支払いが必要です」とAIが案内し、さらにお金を騙し取るケースもあるので注意してください。
手口②:AIで作られた偽ニュースサイト
2023年以降、AIを使って大量の偽ニュースサイトが作られ、世界中で拡散されています。
- 「この投資法で1億円稼いだ!」
- 「有名人がこのダイエット法を推薦している!」
といった誤情報をAIが自動生成し、広告収入を得るためにクリックを誘導しているのです。
AIの作った偽ニュースに騙されないためにも、常にファクトチェック・引用源を確認するクセを付けておきましょう。
手口③:AIで作られた偽の音声や動画
最近では、家族や友人の声をAIで再現し、詐欺を行うケースも増えています。
- 子どもの声を真似て「事故に遭ったからお金を送って!」と親に連絡
- 上司の声を使って「今すぐ送金して」と部下に指示
このような詐欺が急増しています。
さらに、中国では、偽のビデオ通話で約8400万円が騙し取られた事件もありました。
ディープフェイク技術を使った詐欺動画にも注意しましょう。
実際に起こった生成AI詐欺事件

生成AIを悪用した詐欺は、すでに世界中で発生しており、被害額も年々増加しています。
ここでは、実際に発生した詐欺事件を計3つ紹介します。
1. 俳優・ブラッド・ピットのなりすまし詐欺:1億3000万円の被害
フランスの女性が、AIを利用した偽のブラッド・ピットに騙され、約1億3300万円を失いました。
事件のきっかけはSNSです。ある日、被害者の女性がインスタグラムを始めると、「ピットの母」と名乗る人物から「あなたのような女性を探している」と連絡がありました。その後、ブラッド・ピット本人を装った詐欺師が登場し、彼女は彼との特別なつながりを感じ、やりとりを続けたのです。
詐欺師は巧みに女性の信頼を得ながら、「離婚手続きのせいで口座が凍結されている」「豪華なプレゼントを送りたいが関税が払えない」と次々と理由を作り、送金を要求しました。さらに、AIで作られた病床の写真を送り、「腎臓がんの治療費が必要」と訴えました。
女性は1年半もの間、ブラッド・ピットとの関係を信じ込み、最終的に約1億3000万円以上を送金したのです。さらに、詐欺師はFBIを装い「捜査に協力するために追加の支払いが必要」と持ちかけました。ここで女性が不審に思って警察に相談し、詐欺だと気づいたのです。
この事件が報道されると、SNSでは「信じられない」と嘲笑する声も多くありました。
しかし、多くの専門家は「誰でも騙される可能性がある」と警告しています。
参考記事:https://www.bbc.com/japanese/articles/cg45zgkg2l6o
2. 香港の企業で発生したディープフェイク詐欺:約25.6億円(2億香港ドル)を送金
2024年、香港の多国籍企業の財務担当者が、AIを悪用したディープフェイク詐欺により、約38億円を送金してしまいました。
詐欺師らはCFO(最高財務責任者)や同僚を装い、AIで作った偽のビデオ会議を開催しました。画面に映る上司たちは本物そっくりで、声や表情までリアルに再現されていました。担当者は何の疑いも持たず、15回にわたり送金指示に従い、合計5つの銀行口座へ資金を振り込んでしまったのです。
その後、本社に確認した際に詐欺だと判明。この事件は香港初の大規模なディープフェイク詐欺として話題になり、多くの企業がビデオ会議での本人確認強化を検討するきっかけとなりました。
AI技術が進化するにつれ、こうした「映像を悪用した詐欺」が増える可能性があります。本物と区別がつかないため、オンラインのやりとりだけで重要な決定をしないことが重要です。
参考記事:https://edition.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk/index.html
3. 中高生が生成AIを悪用し、携帯回線を不正契約
日本では、中学生と高校生の3人がAIを悪用したプログラムを作成し、通信回線を不正契約する事件が発生しました。
逮捕されたのは、岐阜県・滋賀県・東京都に住む15〜16歳の少年たち。彼らはAI技術を駆使して楽天モバイルのシステムに不正ログインし、100以上の通信回線を不正に契約して転売で利益を得ていました。
さらに、得た資金で暗号資産(仮想通貨)を購入し、オンラインカジノに使用していたのです。犯行の動機は「高度な犯罪を考案し、SNSで注目を集めたかった」というものでした。
この事件は、AI技術が一般の若者にも使われる時代になったことを象徴しています。
SNSで知識を得て、不正アクセスや詐欺に手を染めるケースが増えているため、ネットリテラシーの向上が急務となっています。
参考記事:https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20250227/1000114634.html
生成AI詐欺に遭わないために意識すべきポイント5つ
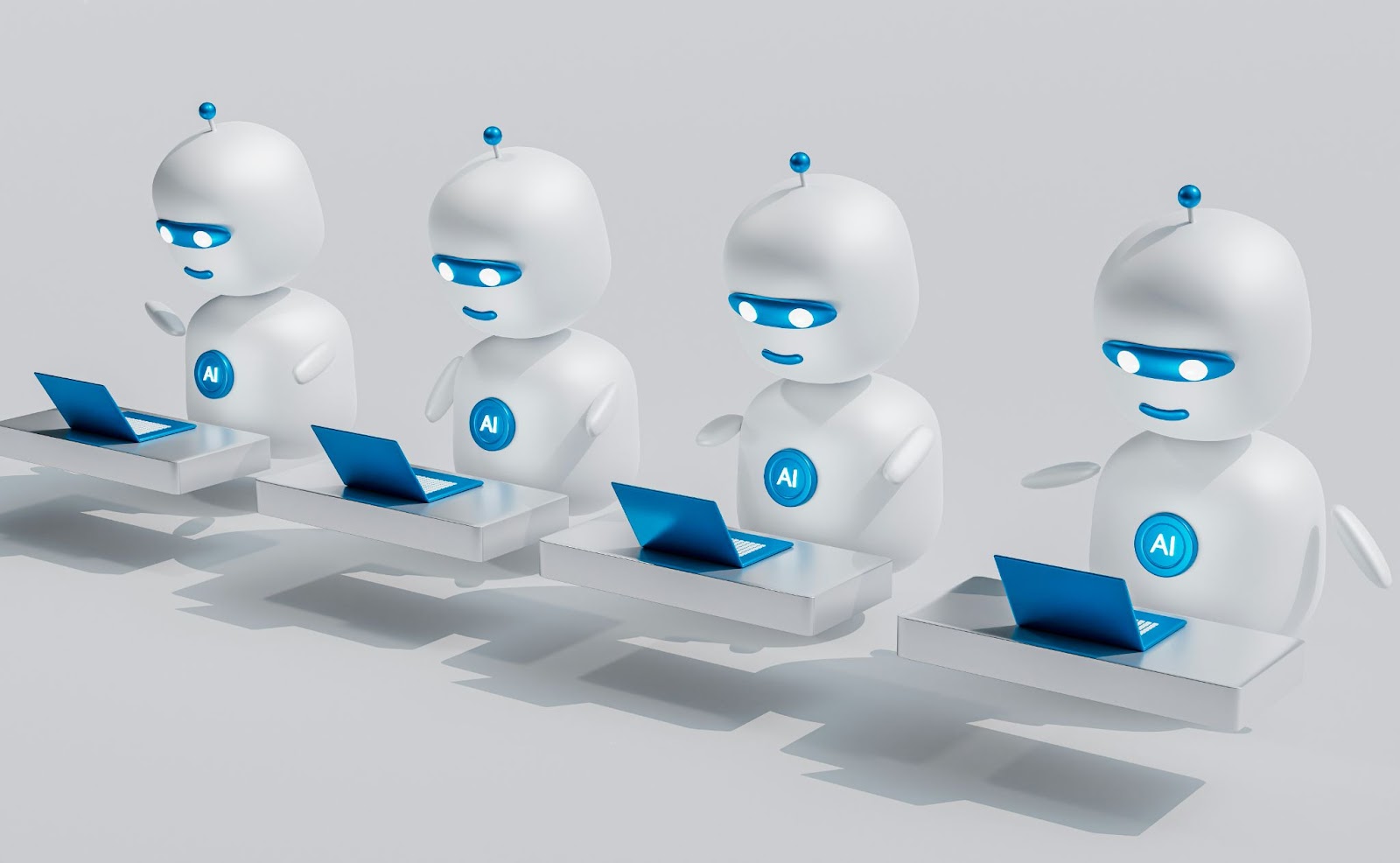
生成AIを使った詐欺は日々進化しており、従来の常識では見抜けない手口が増えています。
知らないうちに騙されないために、意識しておくべきポイントを紹介します。
- 少しの違和感を見逃さない
- 日本語の不自然さをチェックする
- AI技術や最新の詐欺手口を把握する
- 家族や友人と定期的に連絡を取る
- AIに詳しい専門家に相談する
ひとつずつ見ていきましょう。
ポイント①:少しの違和感を見逃さない
生成AIで作られた文章や画像は非常にリアルですが、よく見ると違和感があることが多いです。
例えば、AIが作成した文章は意味が通じるけれど、不自然な言い回しが含まれていることがあります。
また、画像や動画の細かい部分をよく見ると、おかしなところが多いです。
- 指の数・形がおかしい
- 文字が崩れている など
こちらの記事でも「AIで生成された画像は、ポートレート写真のように綺麗にまとまりすぎる傾向にある」と指摘しています。
参考記事:https://www.fuze.dj/2024/08/the-nature-of-the-discomfort-with-photos-created-by-generative-ai.html
少しでも違和感を覚えたら、慎重に対応することが大切です。
ポイント②:日本語の不自然さをチェックする
生成AIの詐欺メッセージは、AIが作った文章をそのまま使っていることが多いため、微妙に不自然な日本語になっているケースがあります。
たとえば、以下のような特徴があります。
- 言葉の使い方が微妙にずれている(例:「ご安心くださいませ」「特別なオファーです」など)
- 日本語として意味は通じるが、どこか違和感がある(例:「お客様のアカウントが問題を抱えています」→通常は「お客様のアカウントに問題があります」)
少しでも不自然な日本語を感じたら、そのメッセージが本物かどうかを冷静に考えてみることが大切です。
ポイント③:AI技術や詐欺の最新情報を知っておく
生成AIの技術は急速に進化しており、今では1枚の写真からリアルな動画を生成できる技術も登場しています。
そのため、「こんな詐欺手口はありえない」と思っていると、簡単に騙されてしまいます。
特に、AIを使った詐欺は今後さらに増えていく可能性が高いため、ニュースや最新情報をチェックすることが大切です。
「AI詐欺 事例」などのキーワードで検索すると、新しい手口が報道されていることもあります。
情報を知っておくだけでも「これは怪しいかも」と疑うきっかけになり、詐欺被害を防ぐことにつながります。
生成AIで最も知名度のある「ChatGPT」の使い道は、本当に幅広いです。
仕事や日常の作業に生成AIを活用する方法を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
ポイント④:家族や友人と定期的に連絡を取る
生成AIを悪用した「なりすまし詐欺」は、家族や親しい人を装って金銭を騙し取る手口が増えています。
特に、親が子どもの声をAIで再現され、「事故に遭った」「誘拐された」などと連絡が来るケースもあります。
こうした詐欺に騙されないためには、普段から家族や友人と定期的に連絡を取ることが重要です。
たとえば、「急な連絡が来たときの確認方法」を事前に決めておくと、不審なメッセージに冷静に対応できます。
また、詐欺師は「あなたを焦らせる」ことが目的です。
「今すぐお金を振り込んで」などと言われたら、一度落ち着いて、本人に直接確認するのが確実です。
ポイント⑤:AIに詳しい専門家に相談する
生成AIを使った詐欺は、見破るのが難しいケースも多く、一人で判断すると騙されやすいのが現状です。
特に、お金が関わる話や、副業・投資などの案件では、第三者の意見を聞くことが重要です。
最近では、AI詐欺について無料で相談できる窓口も増えています。
「この話は本当なのか?」と少しでも不安に思ったら、信頼できる人や専門機関に相談してみるのが安心です。
弊社「吉和の森」では、無料相談で生成AIの使い方や危険性などについてレクチャーしています。
お気軽にご相談ください。
まとめ:生成AI詐欺から身を守るために、最新情報を常にチェックしよう
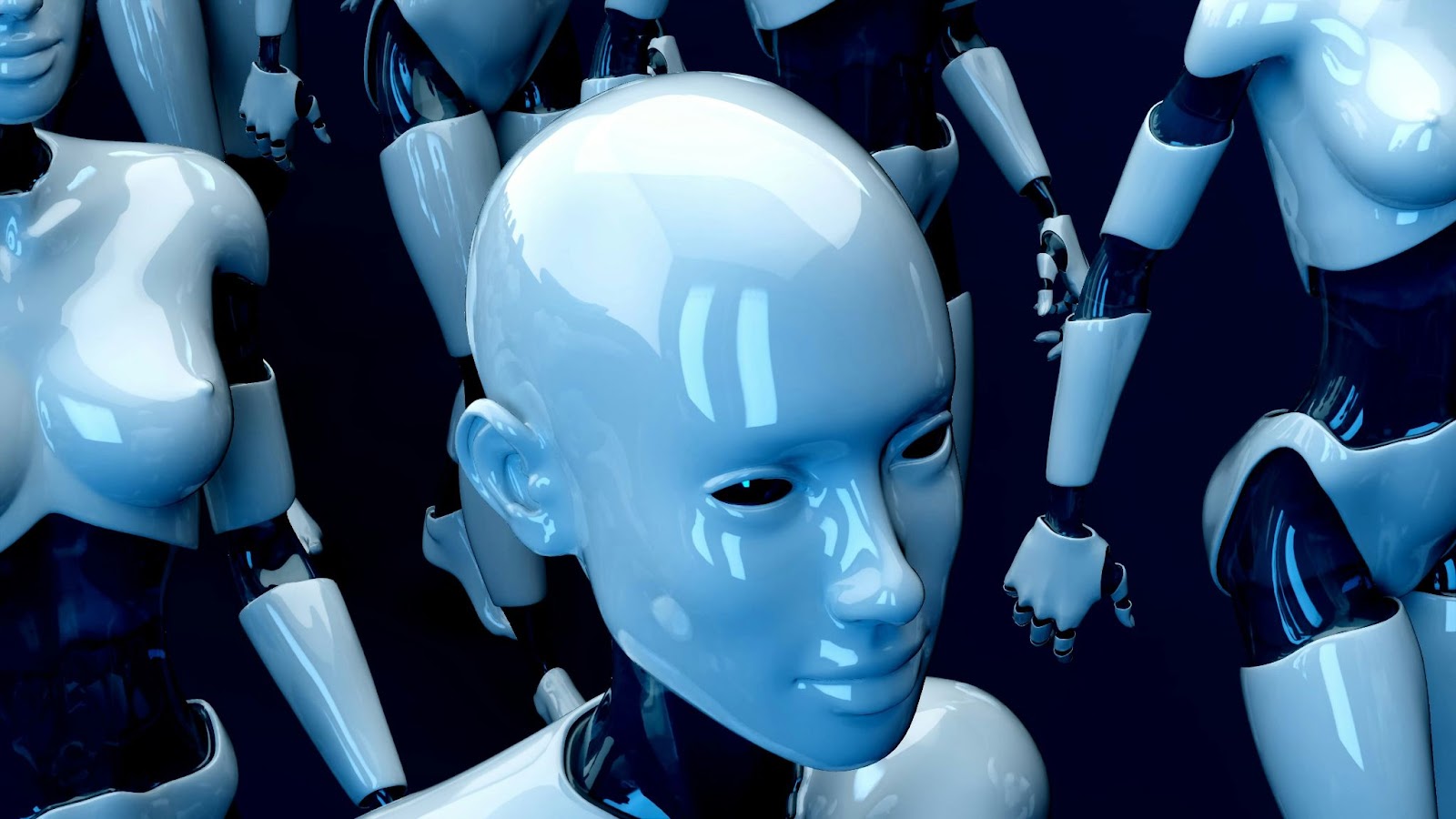
生成AIを悪用した詐欺は増加しており、音声や映像を偽装する手口が特に巧妙化しています。
家族や上司になりすまし、金銭を騙し取るケースも多発。AIで作られた偽のニュースや投資広告にも注意が必要です。
少しの違和感を感じたら「疑う」くせをつけ、生成AIを安全に活用していきましょう。
「これって詐欺?」と不安に思ったら、吉和の森へ相談していただくのもOKです。
30分の無料相談で、AIに関する疑問や詐欺の対策をサポートします。






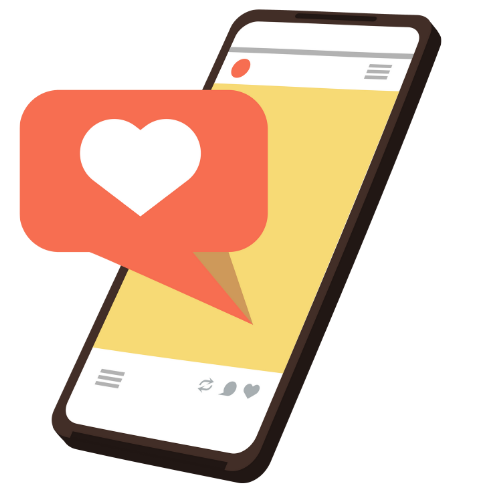
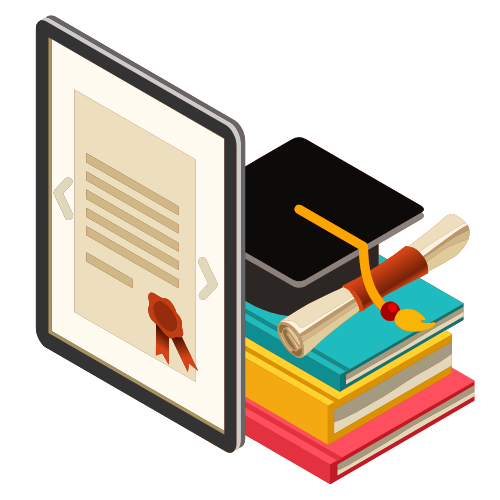
 株式会社 吉和の森
株式会社 吉和の森