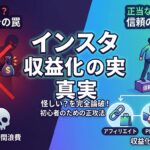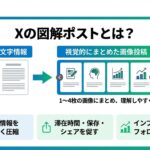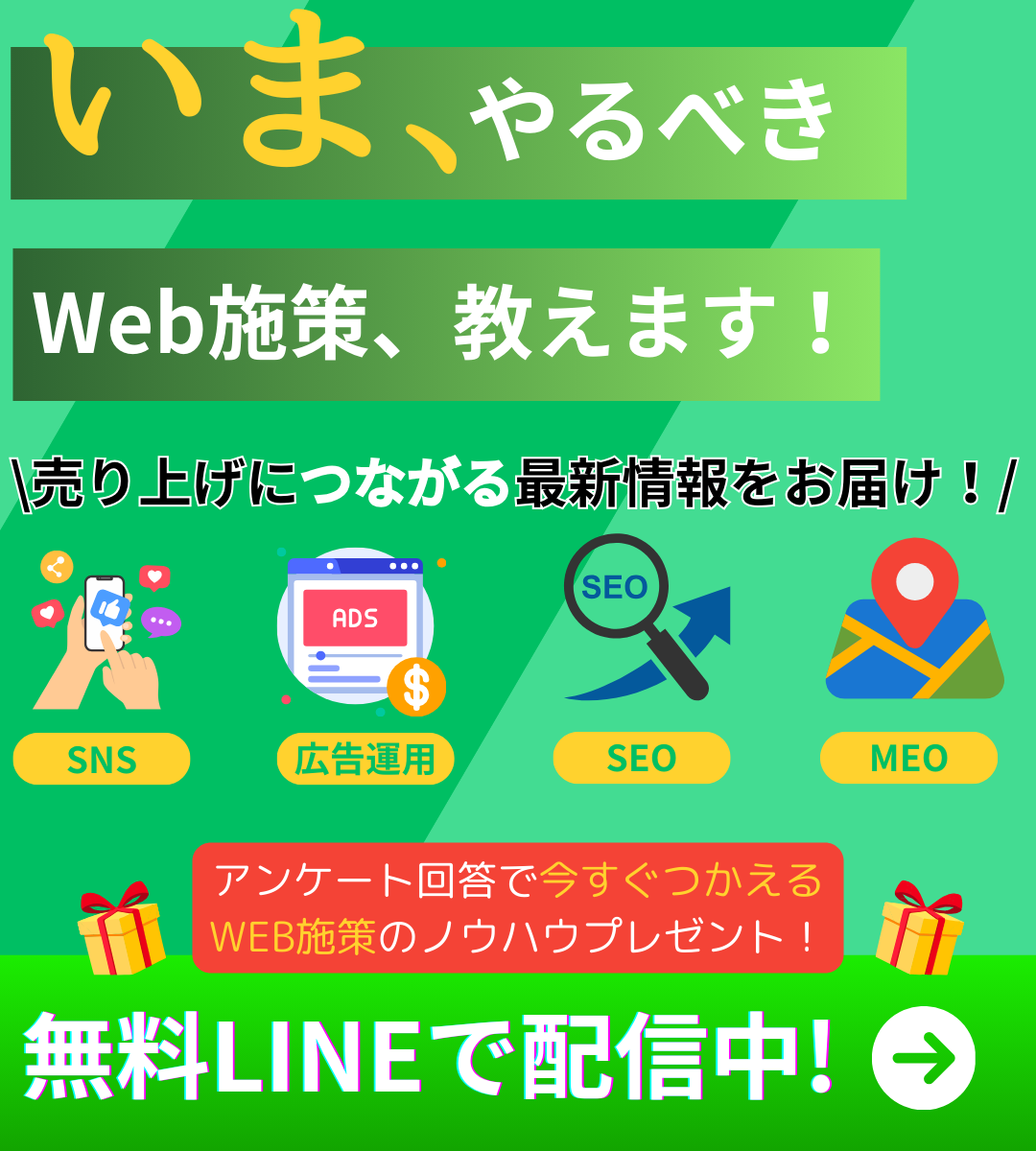「AIのニュースやツールは毎日のように更新され、追いかけるだけで時間が溶けてしまう」
そんな悩みを抱えていませんか。
2026年、AIの情報量はもはや個人の処理能力を超えていますが、だからこそ『誰の視点を通した情報か』という、情報の目利き役(インフルエンサー)の価値がかつてなく高まっています。
今回は、AI専門の筆者が国内外のトップインフルエンサー30名を厳選し、信頼できる最新情報を誰から得るべきかを整理しました。
この記事を読むことで、ビジネスに役立つ実践的な知識を効率よく身につけられます。
AIインフルエンサーをフォローするべき理由3つ
AIの情報収集に悩んでいる方のために、まずはインフルエンサーをフォローする3つのメリットをご紹介します。ただ情報を得るだけでなく、学習効率や実務への応用力が大きく変わります。
ここでは特に重要な3つの理由を、具体例とともに詳しく解説します。
理由1:情報の鮮度とスピードが圧倒的に高いから
AIインフルエンサーの最大の強みは、情報の速さにあります。ChatGPTの新機能やGoogleの最新AI発表など、重要なニュースを従来のメディアより数時間から数日早く知ることができます。
例えば、OpenAIが新しいGPTモデルを発表した際、専門インフルエンサーは発表と同時に実際の使用感や活用法をリアルタイムで共有してくれるのです。AIツールのアップデート情報や新サービスのβ版リリースなど、ビジネスに直結する情報も迅速に入手できます。
こうした鮮度の高い情報により、競合他社よりも一歩先のAI活用を進められるでしょう。
理由2:専門家の思考や文脈(コンテキスト)を理解できるから
AIインフルエンサーが提供するのは、単なる情報の羅列ではありません。その背景にある技術的な解釈や、業界での位置づけなど、専門家ならではの深い洞察を得られます。
たとえば「新しいAIモデルが発表された」というニュースがあっても、それが既存技術とどう異なるのか、どの業界に影響を与えるのかは、専門知識がなければ判断が難しいでしょう。しかし、経験豊富なインフルエンサーであれば、「この技術は製造業の品質管理に革新をもたらす可能性がある」といった具体的な示唆を得られます。
専門家が複雑なAI技術を噛み砕いて説明してくれるため、初心者でも理解しやすくなります。技術的な内容を実践的な視点で噛み砕いて説明してくれるため、非エンジニアでもAIの本質を理解しやすいのです。
理由3:自分の目的に合った情報源を効率よく見つけられるから
AIインフルエンサーには、それぞれ得意とする分野や専門領域があります。
- マーケティング特化
- エンジニア向け
- 経営者向けなど
多様な切り口で情報発信されているため、自分のニーズに最適な情報源を選択できます。
複数の専門家をフォローすることで、同じテーマに対する異なる視点や意見を比較できます。これにより、一方的な情報に惑わされることなく、バランスの取れた判断力を養えるでしょう。限られた時間でも、質の高い学びを得ることができます。

『デジタル・マーケティング超入門』の著者が
「Web集客の仕組み」で売上を創ります
【国内編】日本のAI活用をリードするインフルエンサー13選

日本国内でも、AIを活用しながら実践的な情報を発信するインフルエンサーが多く活躍しています。ここでは、YouTubeで学べる実務家から研究者、現場志向の起業家まで、AI活用の最前線を走る13名を分野別に紹介します。信頼できる国内の情報源を探している方は必見です。
YouTubeで有名なAIインフルエンサー5選
動画で学べるのは、AIを実務に落とし込むうえで非常に有効です。ここでは、視覚的に理解しやすい情報を発信している人気のYouTuberを厳選しました。
KEITO【AI&WEB ch】
「KEITO【AI&WEB ch】」は最新のAIツールの使い方を初心者にもわかりやすく解説するYouTuberです。AIツールを実演しながら、非エンジニアでも再現できる工夫を紹介しています。Web制作とAIを組み合わせた実践的な提案が多いのが特徴です。
ウェブ職TV
「ウェブ職TV」は、ブロガー出身で株式会社メリルの代表取締役・中島大介氏が運営するYouTubeチャンネルです。未経験からプロまでを対象にしたSEO情報を発信しており、それに加えて、AIツールや業務活用スキルを段階的に解説してくれています。自ら運営するAIコミュニティでは、AI仲間との情報交換も可能。実務ですぐ使える内容が多く、現場志向の方にぴったりです。
中嶋聡
「中島聡のLife is Beautiful」は13年以上にわたりAI技術の動向を有料メルマガで深掘りしてきたベテランエンジニア中嶋聡さんのチャンネルです。GPT-4など最新モデルも、プログラマー目線で本質を解説します。米国在住の経験を活かし、グローバルな視野からの発信が魅力。信頼性の高い長期的な情報源として、多くの技術者に支持されています。
AI様の下僕
「AI様の下僕」は顔出し・声出しをせずに、AI編集で魅力的な動画を作るスタイルが注目されているYouTuberです。短くテンポの良い動画で、AIを活用した効率的なコンテンツ制作の実例を多数紹介。エンタメ系でもAIが活用できることを体現しており、ジャンルを問わずヒントが得られるアカウントです。
mikimiki web スクール
「mikimiki web スクール」は日本初のCanva公式アンバサダーとして、AIとデザインを組み合わせた教育コンテンツを発信しています。初心者向けのチュートリアル動画や質問対応付きオンライン講座を提供し、誰でも安心して学べる環境を整えています。CanvaのAI機能をいち早く教材化し、企業研修にも活用できる実践的な知識が満載です。
学術的視点からAIを読み解く!大学教授・研究者3選
最先端のAI技術は、大学や研究機関でも日々アップデートされています。ここでは、研究成果を社会に発信し、教育や産業界との橋渡しを担う著名な研究者を3名ご紹介します。
松尾 豊(東京大学 教授)
「松尾豊」氏は、深層学習(ディープラーニング)とウェブマイニングを専門とし、日本におけるAI基盤技術の第一人者。東京大学教授でありながら、ソフトバンクの社外取締役や日本ディープラーニング協会理事長としても活躍。研究成果をわかりやすく社会に伝え、AI教育の普及に努めています。産業界との連携も積極的に進めており、ビジネスと研究の架け橋として信頼されています。
杉山 将(理化学研究所センター長/東京大学 教授)
「杉山将」は統計的機械学習とデータマイニングの権威で、変化する環境に適応するアルゴリズムの研究において国際的評価を得ています。理化学研究所では大規模データ解析の基盤技術を開発し、東京大学でも教育と研究の両立に努め、『機械学習のための確率と統計』など多数の専門書を執筆・監修し、教育現場でも高い影響力を持っています。国際学会での発表も多く、常に第一線に立ち続けています。
黒橋 禎夫(京都大学 教授/国立情報学研究所 所長)
「黒橋禎夫」は自然言語処理(NLP)の分野で世界的に知られる研究者。日本語に特化した大規模言語モデル(LLM)の開発を主導し、2023年には国立情報学研究所の所長に就任しました。言語による知識処理システムの構築や、AI倫理への貢献も評価されています。国内外の研究者と連携しつつ、日本製LLMのオープンソース化を推進。教育・研究・社会実装の3本柱で、NLPの未来を切り開いています。
実務に直結する知見を発信!開発者・起業家5選
AIを実際のビジネスに活用するには、現場で試行錯誤を重ねた実践知が欠かせません。ここでは、企業導入・教育・サービス開発などに関わりながら、日々の発信を通じて“すぐに使えるAI活用法”を提供している実力派の起業家・開発者を紹介します。
深津 貴之(The GUILD)
「深津貴之」はプロンプトエンジニアリングと法務領域を融合させた、生成AI活用の第一人者。企業向けにセミナーや戦略コンサルティングを行い、プロンプト設計の実務活用を体系化しています。「深津式AIラボ」では、法務部門の業務効率化に役立つプロンプト解説を行い、DX推進を支援しています。2025年には『AI×法務の実務ガイド』を共著し、リスク対策の観点からも高評価。
国光 宏尚(gumi / Thirdverse CEO)
「国光宏尚」はVR・Web3・AIの融合領域で事業を展開する先駆的起業家。Thirdverseでは日米をまたいでVRゲーム開発を牽引し、Web3のDAOやトークン経済を活用し、新たな経済圏の構築に取り組んでいます。2021年には20億円超の資金調達に成功。Microsoftなどの海外企業とも提携し、国際的な技術展開を行っています。メタバースとAIの実用化に関する情報発信も積極的で、政府との連携実績も豊富。
木内 翔大(SHIFT AI 代表)
「木内翔大」は国内最大級のAIコミュニティ「SHIFT AI」(会員2万人以上)を運営。教育とビジネスをつなぐコンテンツを多数展開しており、企業研修から個人学習まで幅広く対応。特にXでの発信では、日々最新のAIツール活用事例を紹介しており、現場に直結する実践的な知見が豊富です。図解やステップ付きの投稿も多く、初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。
臼井 拓水(Michikusa代表/デジタルハリウッド大学 特任准教授)
「臼井拓水」は生成AIの実務活用と教育に特化した専門家。100社以上の法人研修実績を持ち、大学ではAI人材育成のカリキュラムを構築。40時間以上にわたる動画教材と体系的な講座を整備し、基礎から応用まで幅広く学べる環境を提供しています。注目すべきは、業務を自動化するAIエージェントの仕組みをわかりやすく解説している点です。技術的な知識に加え、実用例を交えて教えてくれる点が特長です。
大野 峻典(Algomatic CEO/東大松尾研出身)
「大野 峻典」は東大・松尾研究室出身の連続起業家として、複数のAIスタートアップを立ち上げた実績を持つ人物。企業向けに「AI導入のフレームワーク」を提供し、戦略設計から導入、実装までの一貫支援を行っています。長期的な視点を重視し、技術の本質とビジネスモデルの整合性を重視した提案が強みです。現場で使えるAI戦略を求める企業にとって、実務的かつ先見性のある情報源です。
【海外編】世界のAIトレンドを牽引するインフルエンサー19選

AIの最先端は今、世界規模で急速に進化しています。日本国内の情報だけでは見えにくい潮流も、グローバルな視点を持つインフルエンサーをフォローすれば、いち早くキャッチできます。ここでは、研究者・起業家・メディアの3カテゴリに分けて、国際的に影響力のある人物19名を厳選して紹介します。
AIの未来を創る!研究者・開発者系インフルエンサー5選
AI技術の礎を築いた研究者や、実用的なAI教育に取り組む開発者たちは、まさに未来の扉を開くキーパーソンです。ここでは、技術と教育の融合に取り組みながら、世界に影響を与える研究者・開発者を5名紹介します。
Andrej Karpathy(アンドレイ・カルパシー)
「Andrej Karpathy(アンドレイ・カルパシー)」はOpenAI共同創設者であり、TeslaのAI部門元ディレクターという経歴を持つ実力者です。現在はAI教育企業「Eureka Labs」を創設し、LLM(大規模言語モデル)教育プログラム「LLM101n」を開発しています。初心者にも理解しやすい内容で、AIリテラシーの底上げに貢献しています。スタンフォード大学の講師としても活躍し、YouTubeで実践的な学習コンテンツも展開。教育と実務の橋渡し役として要注目です。
Andrew Ng(アンドリュー・ウン)
「Andrew Ng(アンドリュー・ウン)」はDeepLearning.AIの創設者であり、Courseraでのオンライン講座「AI for Everyone」は日本語対応で世界的に人気。Google BrainやBaiduでの研究経験も持ち、AI教育の民主化に大きく貢献しています。非エンジニア層でも理解しやすい教材設計が特徴で、企業のDX推進においても広く活用可能。AIを社会全体で活かすための視点と実践が詰まっており、信頼性の高い情報源として多くの支持を集めています。
Geoffrey Hinton(ジェフリー・ヒントン)
「Geoffrey Hinton(ジェフリー・ヒントン)」は深層学習の祖として知られ、「誤差逆伝播法」などのAI基盤技術を開発した先駆者。2024年にはノーベル物理学賞を受賞し、その社会的影響力は計り知れません。AIの進化におけるリスクについても警鐘を鳴らしており、「30年以内に人類が絶滅する可能性」など、倫理・政策的視点での発信も多い人物。技術と社会課題を両立して考えるうえで、フォローしておきたい存在です。
Demis Hassabis(デミス・ハサビス)
「Demis Hassabis(デミス・ハサビス)」はDeepMindの創設者で、AlphaGoやAlphaFoldなど、AI技術で科学や医療に革新をもたらした立役者。2024年にはタンパク質構造予測の功績でノーベル化学賞を受賞。日本の製薬企業とも連携しており、実用的なAI応用が評価されています。ゲーム開発出身という異色の経歴を持ち、創造性と科学の融合が特徴。AGI(汎用人工知能)に向けた長期ビジョンも掲げており、未来を見据えた視点を持つ人物です。
Yann LeCun(ヤン・ルカン)
「Yann LeCun(ヤン・ルカン)」はMeta(旧Facebook)のチーフAIサイエンティストであり、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)の開発者。自己教師あり学習(Self-Supervised Learning)の推進者として、次世代AIの可能性を広げています。大規模言語モデル(LLM)への懐疑的な視点を持ち、「世界モデル」の必要性を主張。科学的根拠に基づいた冷静な分析と提言は、日本のAI研究にも示唆を与える内容が多く、技術的バランス感覚に優れた人物です。
AIビジネスの最前線!起業家・投資家系インフルエンサー5選
AI技術を社会実装し、ビジネスとして成立させるには、技術だけでなく市場や戦略に精通した起業家や投資家の視点が不可欠です。ここでは、AIスタートアップの創業や投資、実務的なサービス展開を通じて、世界のAIビジネスを牽引している5人を紹介します。日本企業にも応用できるヒントが満載です。
Sam Altman(サム・アルトマン)
「Sam Altman(サム・アルトマン)」はOpenAIのCEOとして、ChatGPTをはじめとするAI技術の社会実装を推進。日本法人「OpenAI Japan」の設立により、日本市場への本格参入も果たしました。GPT-4の日本語最適化や、AIエージェント(バーチャル従業員)の普及にも注力。元Y Combinator代表としてスタートアップ支援の実績も豊富で、技術と経済の融合を実現する戦略的視点が高く評価されています。日本のDX戦略にも直結する存在です。
Satya Nadella(サティア・ナデラ)
「Satya Nadella(サティア・ナデラ)」はMicrosoftのCEOとして、生成AIを組み込んだ「Copilot」シリーズを展開し、世界中の企業にAI導入を促進。2025年には日本を訪問し、AIによる経済成長戦略を発表。日本語対応の強化も進め、国内業務での実用性を高めています。「今やコードの30%はAIが書いている」と明言するなど、AI実装の現実味を強く訴求。組織改革・人材戦略にまで踏み込んだ発信は、日本の経営層にも響く内容です。
Jensen Huang(ジェンスン・フアン)
「Jensen Huang(ジェンスン・フアン)」はNVIDIAのCEOで、GPU技術によってAI革命の基盤を築いた人物。AI専用半導体「Blackwell」シリーズを通じて、ハードウェア面からの革新をリードしています。日本政府と連携し、国内でのAI基盤整備や人材育成を支援。「使い捨てしない」採用哲学や、フラットな組織運営など、経営スタイルにも注目が集まります。技術と経営、両輪での影響力があり、日本企業の変革に深い示唆を与えています。
Marc Andreessen(マーク・アンドリーセン)
「Marc Andreessen(マーク・アンドリーセン)」は伝説的なベンチャーキャピタリストで、a16z(Andreessen Horowitz)の共同創設者。2025年にはAI特化型ファンドを200億ドル規模で立ち上げ、日本市場への投資強化も明言。Webの普及を牽引した先見性をもとに、次世代AIトレンドを先読みする発言力があります。「ソフトウェアが世界を食べる」の提唱者でもあり、テクノロジーの本質的な価値創出を強調。グローバル視点での情報発信は必見です。
Elon Musk(イーロン・マスク)
「Elon Musk(イーロン・マスク)」はTeslaやSpaceXの創業者として有名ですが、AI分野でもxAIを立ち上げ、独自路線で存在感を示しています。Grokシリーズでは、日本語対応を強化し、中小企業でも活用できるAIを追求。SNS「X(旧Twitter)」と統合し、AI・情報・メディアを融合させる大胆な戦略を展開。AI業界の既存秩序に挑戦する姿勢は、破壊的イノベーションそのもの。OpenAIとは異なる視点から、選択肢を広げる存在です。
最新ニュースを速報!AI専門解説者・メディア4選
AIの世界では、日々新しいツールやサービス、研究成果が登場します。こうした情報をいち早くキャッチし、わかりやすく解説してくれるのが専門メディアや情報系インフルエンサーです。ここでは、速報性と実用性を兼ね備えた信頼できる解説者・メディアを4つ厳選してご紹介します。
Rowan Cheung(The Rundown AI)
「Rowan Cheung(The Rundown AI)」はAI専門のニュースレター「The Rundown」を毎日発行。わずか5分で最新情報のポイントと活用法が理解できる構成で、すでに100万人以上の読者を持ちます。OpenAIやGoogleのリリース内容も即時に解説し、実務にどう使えるかまで言及。ポッドキャスト「The State of AI」では業界のキーパーソンと対談を行い、戦略的な視座からの分析も提供。英語圏の情報を噛み砕いて届けてくれる貴重な存在です。
Matt Wolfe
「Matt Wolfe」はYouTubeやXを中心に、最新AIツールを実演レビューする人気クリエイター。HeyGenなどの話題ツールを実際に使って見せるスタイルで、視覚的に理解しやすく、業務への応用がイメージしやすいのが特長です。AIエージェント市場の動向についても投資家視点から鋭い分析を行い、企業の戦略立案にも役立ちます。英語圏のコンテンツを日本語圏向けに再構成する工夫も見られ、多言語ユーザーへの配慮も行き届いています。
Lex Fridman
「Lex Fridman」はMITの研究員でありながら、自身のポッドキャストを通じてAIと人間の未来を深く掘り下げる対談を多数実施。Yann LeCunやElon Muskなど世界的な研究者・起業家との2〜3時間に及ぶ本格的なトークで、技術だけでなく倫理・社会実装の視点まで幅広く扱います。日本語字幕付きで公開されており、英語が苦手な人でも安心。AIを単なるツールで終わらせず、「人間とどう共存するか」を考えるうえで欠かせない情報源です。
a16z(Andreessen Horowitz)
「a16z(Andreessen Horowitz)」はシリコンバレーを代表するVC(ベンチャーキャピタル)で、AIスタートアップへの投資と分析を専門に行っています。定期的に公開する「生成AI TOP100」リストは業界の勢力図を見通すのに最適。企業のCIO向けに行った調査データや、AI×核エネルギーなどの最先端テーマに関するレポートも話題です。ポッドキャストやブログを通じて、経営層・実務者それぞれに向けた深い示唆を提供しています。
AIインフルエンサーの情報を鵜呑みにしない!フォローする際の3つの注意点

信頼できるインフルエンサーを見極めることは、AI情報を正しく活用するうえで非常に重要です。ただし、どんなに有名な人物であっても、その発言を無条件に信じるのは危険です。
ここでは、AIインフルエンサーをフォローする際に注意すべき3つのポイントを解説します。
注意点①:ポジショントークを見抜く
インフルエンサーの発信には、企業やプロダクトとの利害関係が関わっている場合があります。とくにSNSや動画メディアでは、広告案件や提携サービスの宣伝を含んだ投稿も少なくありません。
一見すると客観的に見える情報でも、「なぜこの内容を今発信しているのか?」という背景を意識的に読み取る姿勢が必要です。特定のAIツールだけを強く推奨していたら、それがスポンサー案件でないかを疑ってみてください。発言の裏にある立場や動機に目を向けることで、情報を正しく受け取れるようになります。
注意点②:一次情報を確認する癖をつける
生成AIの普及により、誰もが気軽に情報発信できるようになった一方で、誤情報の拡散リスクも高まっています。たとえば「◯◯のAI機能がアップデートされた」という投稿を見かけたら、引用元や公式の発表にあたって真偽を確認する習慣が重要です。
- 信頼できるソースが明記されているか
- 元情報はどこからか
上記の意識を持って、思わぬ誤解や誤用を防ぐことができます。とくにビジネス活用を前提に情報を取り入れる場合は、「自分の目で裏を取る」意識が不可欠です。
生成AIに関連する詐欺も増えているので、情報を鵜呑みにしないことは大切になってきています。
注意点③:複数の情報源を比較検討する
どれほど影響力のあるインフルエンサーでも、一人の意見だけで全体を判断するのは危険です。AIの分野は多角的で、同じテーマについても専門家ごとに異なる視点や評価があります。
異なる見解を比較検討することで、自分にとって最適な判断が可能になります。情報の偏りを避け、バランスの取れた視野を持つためにも、複数のインフルエンサーをフォローし、視点の多様性を意識的に取り入れましょう。
まとめ

AIの進化が加速する中で、信頼できる情報源を持つことは大きな武器になります。本記事では、国内外の優れたAIインフルエンサーを30名厳選してご紹介しました。
スピーディーかつ実践的な知見を届けてくれる彼らの発信をうまく活用すれば、AI活用の精度と効率が飛躍的に高まります。
ただし、情報は鵜呑みにせず、批判的思考と複数の視点をもって受け取ることも忘れずに。信頼と判断力という2つの軸を持って、AI時代を乗り越えていきましょう。






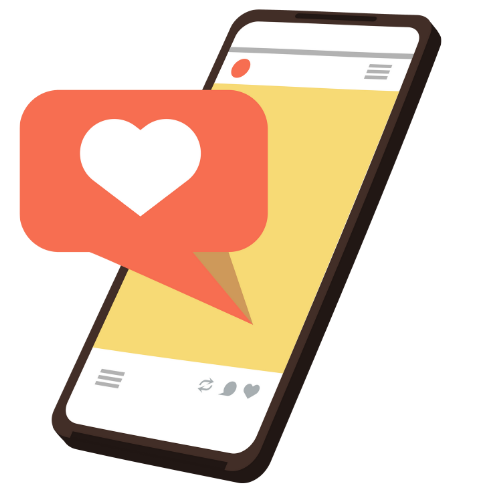
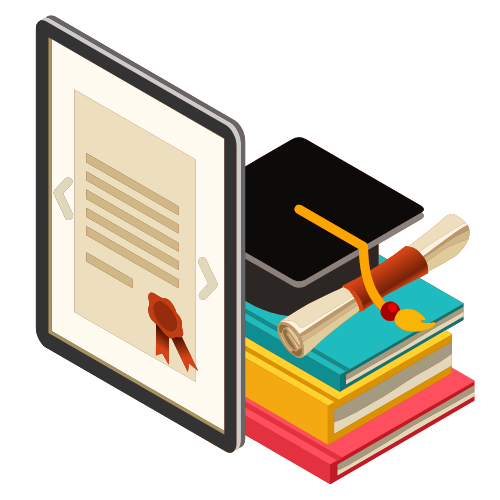
 株式会社 吉和の森
株式会社 吉和の森